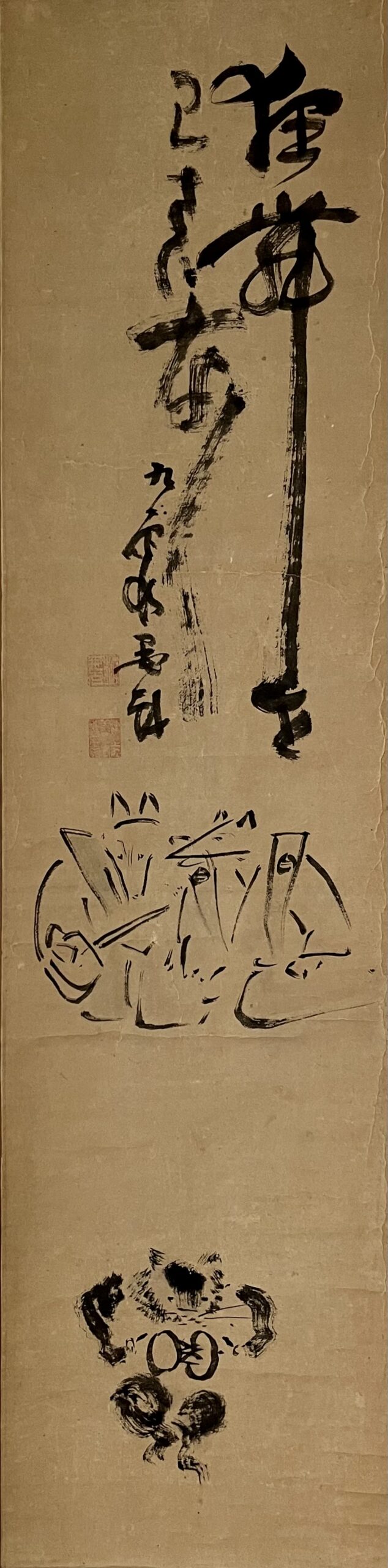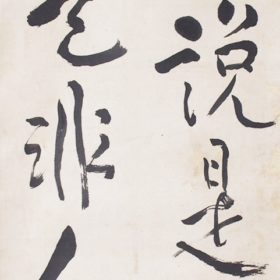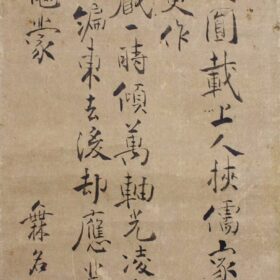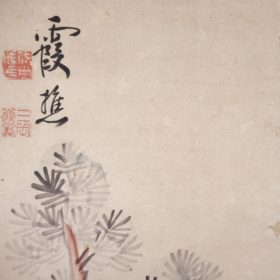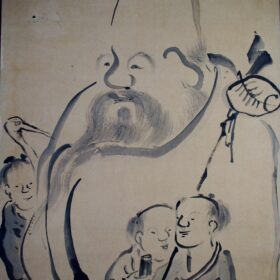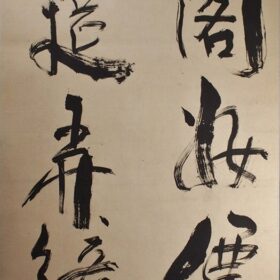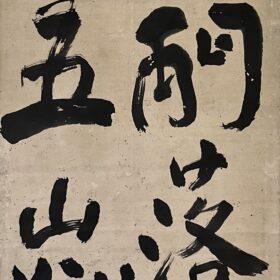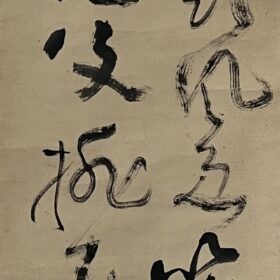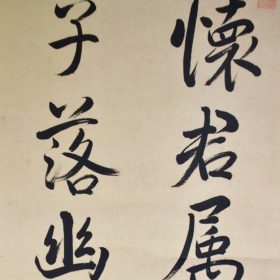本紙 約106 × 26㎝
軸装 約172 × 29㎝
紙本淡彩
□
狸舞せ わさ(技)はなく
九霞墨戯
□
裃を付けた狐が二匹。
一匹は三味線を弾き、
一匹は膝に手を載せて、一曲呻っているようです。
それに合わせて、
狸は踊りながら、
お腹に載せた太鼓を撥で叩いています。
山水画に比べ数は少ないですが、
大雅は戯画・おとぎ話を題材にした作品も描いています。
袴姿に裃をつけて正座する狐と対照的に、
狸は毛むくじゃらな手足をだして滑稽な恰好。
ちょっと肩が上がって両腕を丸くしているのは、
まん丸なお腹を輪郭で表わしているのでしょう。
「狸舞わせ 技もなく」
ってどういう意味でしょう?
(単純な)狸なんか、簡単に躍らせちゃうよ、
(→簡単に他者の言葉に踊らされるな)
の意でしょうか。
大雅は白隠禅師に参禅しています。
臨済さんは
「人に騙されるな、見性せい」
とおっしゃっいました。
その禅の教えを、大雅らしく、
深刻ぶらずに現したのかもしれません。
洒脱な作品です。
シュッとした線のスマートな狐に比べ、
狸はいかにも不細工な姿。
それを、少ない筆致で見事に表現しています。
「墨戯」ー戯れに描いた、と言いながら
深い精神に通じる何かが、
大雅だけしか到達しなかった画力によって現われています。
追記
狂言の演目に「狸腹鼓/たぬきのはらつづみ」があることを、
有識者の方にご教示いただきました。
江戸時代後期に、井伊直弼が古作を改訂し、
通常は「彦根狸」と称され、非常に難しい演目だそうです。
大雅の時代には、古作の狂言として、庶民に親しまれていたのかもしれません。
◆
款《九霞墨戯》
この、「霞」をうんと縦長に書く描き方は、
30才代中~後期の款記です。
いかにも遊びのある姿です。
「池橆名」白文方印
この印章は《白糸瀑布真景図》(個人蔵/2018年京都国立博物館池大雅展図録№114)
に捺されています。
40才頃の作品とされています。
「新嬪面上濡笑靨一宮鏽暮裏行」白文長方印
この印章は、
出光美術館所蔵《布袋童子図》、
《倣董太史富岳図》(個人蔵・2018年京都国立博物館池大雅展図録№112)
に捺されています。
出光作品は20才代末、富岳図は30才代前期の作品と考えられています。
款記の書き方、印章から、
30才代中~後期の作品と推測します。
狐の裃には藍が薄く着色されていて、
センス抜群の一幅です。
大雅堂五世 定亮鑑定書二重箱付
大雅と妻の玉瀾が亡くなったあと、大雅を強く思慕した門人たちは、
二人の住まいのあった真葛ヶ原に《大雅堂》を建て、
大雅の遺愛品・作品を残し伝えました。
本作品で箱の蓋裏に鑑定を書いた定亮は、
その堂主5代目で、大雅作品の鑑定人です。
大雅堂は明治19年(1886)、円山公園の造成に伴いなくなります。
その後、最後の堂主・六世霞邨から大雅の遺品を譲られたのが、
池大雅美術館創立者の佐々木米行氏です。
氏のコレクションは、京都府に寄贈され、現在は京都府蔵となっています。
作品本紙右側に、きつい縦皴がございます。
他にも折れや経年による汚れがございますが、
シミはほとんどなくきれいです。
お問い合わせください。
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら
一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、
その作品を愛藏されていました。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。
□
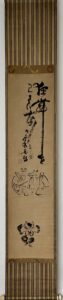
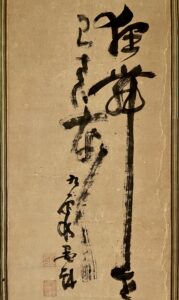
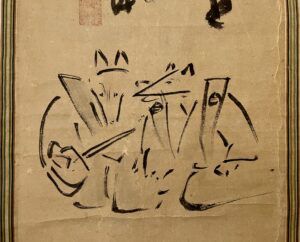
狐の下も折れがございます
□
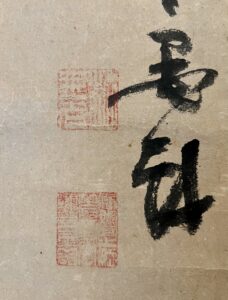


□




□