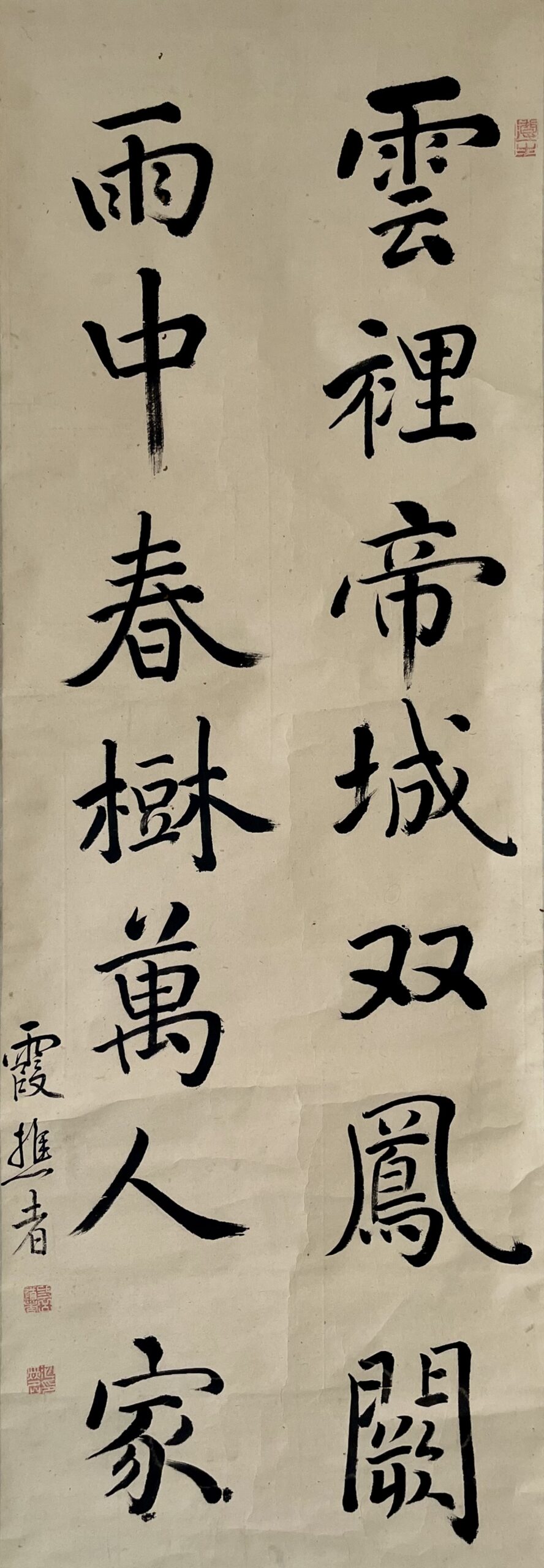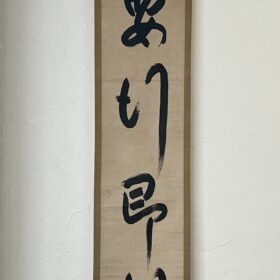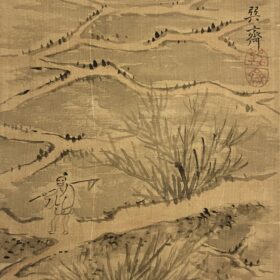本紙 約111,5 ×39,1㎝
軸装 約168 ×34,3㎝
紙本
□
雲裡帝城双鳳闕
雨中春樹萬人家
□
盛唐を代表する詩人・王維(~731)の
「奉和聖製従蓬莱向興慶閣道中留春雨中春望之作応制」
聖製「蓬莱より興慶に向かう閣道中の留春にて、雨中春望の作」に和して奉る応制
の中の二行。
雲の中から帝城は鳳凰の飾りを聳えさせている
雨が降って春の樹々が青々として家々を覆い隠している
□
「聖製」は天子がお作りになられたの意です。
皇帝が作った詩に応えて、王維が作った詩。
霞や雲が立ち込める街を俯瞰し遥々とした視点。
春の雨ですくすくと葉を茂らせる都の家々の樹々。
悠々として清澄な詩です。
楷書で書かれています。
肥痩や、派手な動きのない楷書で魅せることは、非常に難しいこと。
「城」「鳳」「春」の
上から左右に下ろされる筆が丸みを帯びていて、
皇帝の世の繁栄とか、平和とか、
春の心地よさとか、そんなことをそれとはなしに感じさせます。
同じ詩文を横長の紙面に描いた作品が、
池大雅作品集(中央公論美術出版/昭和35年)に所載されています。(作品№743)
某大企業の創業者のご所蔵となっています。
「雲」「裡」「双」「中」はほぼ同じ文字姿です。
《この詩を書く時はこの書き方》が、
大雅の中で定まっていたように思われます。
また、本作品は横幅39,1㎝に二文字、
作品集掲載作品は、縦55,5㎝に三文字配置されていますので、
一文字はほぼ同じ大きさと考えてよいでしょう。
款記「霞樵者」
関防印〈遵生〉朱文長方印は、30才代後期~生涯使われた印章。
「池橆名印」白文方印
「弎岳道者」白文方印
この2印は、30才代後半から使われ始め、40才代で非常に多く使われ、
50才代、最晩年まで使われた印章です。
ペアで捺されることが多いです。
池大雅作品集(昭和35年・中央公論美術出版)掲載682画作品の内、
64作品にこの2印がペアで捺されています。
大雅の書は、江戸時代、お手本として出版物になったほど。
楷書として、芸術的に完成された形に高められた書姿です。