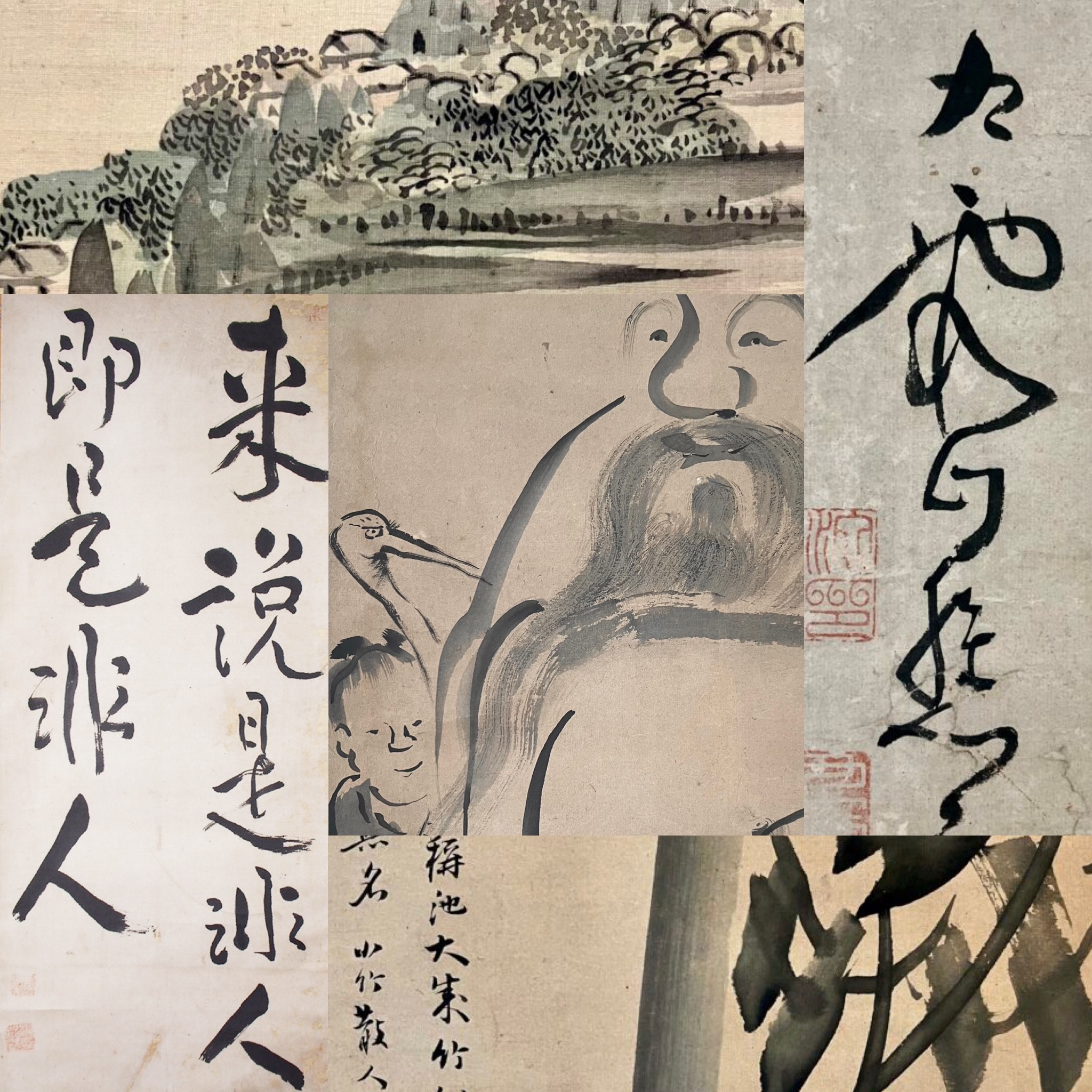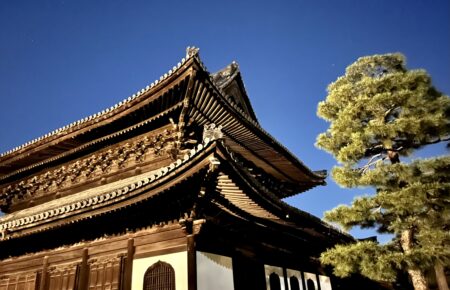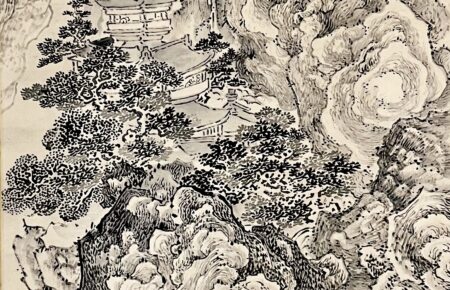5月4日は池大雅の302回目の誕生日!
4/24(木)~5/10(土)
久しぶりに大雅作品の大セール決行いたします!
川端康成、梅原龍三郎、伊東深水、谷川徹三等々
一流の文化人、画家たちが心を鷲摑みされ、愛藏した大雅の作品。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は、
大雅が最も多いことは、現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品。
同じく国宝に指定されている「楼閣山水図屏風」(東博蔵)は、一橋徳川家旧蔵品です。
大雅は多作です。
20才代で有名になり、旅が好きだったので、全国区で大人気!
身分の高い、お金にいとめをつけない依頼者には大作を、
市井の庶民の求めには小品を、
依頼者の求めに応じて様々に作品を制作したんです。
子供の時から亡くなるまで、描くのが書くのが好きで好きで堪らなかった!
リーズナブルでも素晴らしい作品がございます。
誰も傷つけない、
見る者を優しく深く包み、ギュッと強く心を掴んでくれる大雅の書画世界。
この機会に是非ホンモノをお手になさってください!
勿体つけても、宝の持ち腐れ!
30%~最大50%Off!!の大セールです。
◇作品ご紹介◇
◆1◆
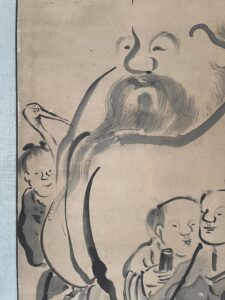
◆南極寿星図◆
三人の童子と鶴を連れた南極老人。
「寿星」とも表わされ、南極老人星を神格化した神様です。
中国では古来、この神様が現れると天下が治まるとされ、
鹿をお供に連れ、
寿命を記した巻き物を持っているのが定番。
本作品では、巻き物は童子の一人が持っていますね。
水分をたっぷり含んだ太い単純な筆致で描かれます。
お鬚と鬢は、極々細い筆跡で柔らかく表現されています。
出光美術館ご所蔵の
【寿老四季山水図(五幅対】(川端康成旧蔵)は、
延宝11年(1761)、大雅38歳の作品で、
五幅の、中心の一幅に、樸童と鶴を伴った南極老人が描かれます。
切れ長で下がった目尻、
細い細い毛足の垂れた眉、
こんもりと柔らかな口髭など、
本作品と非常によく似た表情です。
長い杖に、亀の甲羅のようなものが付いているところも
その杖を童子が持っているのも同じです。
本作品の落款の
《九霞山樵写》の書き方は30歳代後半の姿で、
出光作品と同時期に描いたと考えてよいでしょう。
この後ろで踏ん張っている眼付きの悪い鶴は、
旧池大雅美術館コレクション作品(京都府蔵)にも表れます。
《霞樵》朱文連印
この印章は、30才代から生涯使われ、最も使用頻度の高い印章の一つです。
池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)掲載の画作品では、
682作品中146作品に使用されています。
弊店が入手してから
修復仕立て直ししてございます。
本紙に傷み、皴、汚れがございます。
画像でご確認ください。
◆他の画像はこちらをクリック◆
本紙 110 ×37㎝
軸装 183 × 49,7㎝
紙本墨画
時代箱付
¥495,000 →40%Off ¥297000!
消費税・送料込
◇
◆2◆

◆張籍詩谿居図◆
張籍は唐時代(8~9世紀)の詩人。
作品集・張司業詩集八巻があります。
本作品に書かれた五言律詩は、詩集の中の一つです。
この作品を見た時、すぐに思い浮かんだ作品がありました。
《重文》洞庭赤壁図巻(京都国立博物館蔵)
明和8年(1771)・大雅49歳の作品です。
縦55㎝余りの3m近い巻物で、
本作品と同じく絹本に、
洞庭湖に浮かぶ島々に様々な樹々が繁っています。
こんもりとした樹々の中に、人の住む家の屋根が姿を見せます。
多作な大雅ですが、このような描き方は稀です。
洞庭赤壁図巻においては、非常に濃い着色で、樹々の繁茂を描いていますが、
本作品では透明な色彩に、漆黒の墨で細部を顕しています。
樹木の種類によって描き分けた葉の茂み。
この上なく素晴らしい表現です。
遙かな遠山が、没骨で横に長く長く引かれている手法も、
洞庭赤壁図巻と本作品の共通点です。
図巻(巻き物)は非常に横長な画面ですので、遠山は横に並んでいて、
本作品は縦長ですので、
遠山は縦に並んで奥行きとなっています。
透明感のある奥深い緑の樹々のある水辺の地。
穏やかな谿居の様子、
遙か彼方まで続く景色。
見る者の心に清風が吹き抜ける、なんて気持ちのいい世界。
大雅にしか描けなかった画世界です。
胸が痛いほど美しい。
右上に、手前の崖が姿を見せることで、
額縁のような効果を上げると同時に、
手前からジグザグに画面構成され、
画の中の世界がずーっと遠く、
見えない程遠くまであることを感じさせます。
上質な墨で丁寧に書かれた詩文の書も見事です。
〈深濘池氏〉白文方印
〈橆名〉白文方印
この印章は、年記のある作品では、
「雲林清曉図」宝暦9年(1759/大雅37歳)の作品、
「朝鮮通信使行列図」宝暦14年(1764/大雅42歳)以降、に捺されており、
30歳代と40歳代前期と考えらる作品に捺される印章で、
「深濘池氏」と「橆名」は、
同じ印材の両面です。
関防印の〈遵生〉朱文長方印は、
30歳代後期~生涯使われた印章。
この3つの印章が同時に捺された作品例は、
池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)№200「車前草(オオバコ)図」。
紙本墨画のこの作品には、車前草に、
本作品と同じ張籍の七絶が書され、
「右唐人張籍答開州韋使君寄一絶」と記されています。
大雅の絹本着色作品は数が少ない上に、本作は名品中の名品と存じます。
印章と謹直で充実した筆致から、40歳代前半の作品と考えます。
汚れ、傷みはほぼ見当たりません。
上質な金糸の緞子の中廻し裂に、
金襴の天地一文字裂の表具。
本紙 約97,6 ×33㎝
軸装 約182,5 ×48,9㎝
絹本著色
京都岡墨光堂の口巻紙附属
時代二重箱
¥1,500,000 ⇒50%Off ¥750000!!
消費税・送料込
◇
◆3◆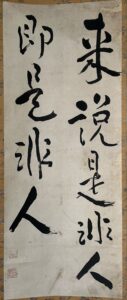 「来説是非人即是非人」
「来説是非人即是非人」
来りて是非を説く人は
即ち是非の人
でしょうか。
右上に関防印、
左下に印章がありますので、
完成された一つの作品であることがわかります。
大雅らしい非常に魅力的な書。
不要な力みが全くなく、
自然体の文字の姿です。
「この方は立派だな」
「人間ができている方だな」
って方は、
全く偉そうにもなさらないし、
厳つい身なりでも、きつい表情もしていない。
声高に主張もしない。
大雅のこの書は、そんな人物のようです。
「人」
という字は、ひときわ濃くはっきりと書かれています。
竹屋町裂がふんだんに使われ、
旧蔵者岩崎巴人(いわさきはじん)の、この作品への尊敬、愛情が感じられます。
関防印の〈遵生〉朱文長方印は、
30歳代後期~生涯使われた印章。
「九霞樵者」白文方印は、
40才代作品に数多く捺され、最晩年まで使われています。
「池橆名印」白文方印は、30才代後半から最晩年まで使用された印章です。
重文・白雲紅樹図(相国寺承天閣美術館蔵)、五君咏図、
瓢鮎図(出光美術館蔵)にも捺されています。
ちなみに、この印章はよく似た陰影の印章が他に2つあるんです。
岩崎巴人(1917~2010/僧侶・日本画家)の極箱付
本紙 65,5 ×26㎝
軸装 140 ×38,2㎝
紙本
¥220,000 ⇒40%Off ¥132000!
消費税・送料込
◇
◆4◆

◆水墨蘭石図双福◆
左幅には、岩から生えたひと際大きな蘭。
豊かな長い葉を、向かって左から吹く風に大きく踊らせています。
なんてダイナミックな動きの描写。
たっぷりと水を含んだ筆の伸びやかなこと!
墨の美しい色に心奪われます。
蘭の花が、植物というよりも、小動物か昆虫の顔のようなのも、
大雅の特徴の一つでしょう。
画の中で生きて蠢くようです。
右幅がこれがまた素晴らしい!
こんな大雅作品、他にあったかしらと思います。
右幅の主役は、大きく複雑な穴を持った太湖石です。
胸騒ぎを覚える、奇奇怪怪な姿。
青墨で、水分たっぷりの太い太い筆で描かれた岩の輪郭と、
割れた筆先で幾重にも奥ゆきを表現した複雑な穴、
その穴から、うるうると見える裏側の蘭。
異世界へ連れて行かれそうです!
岩の側面に生える蘭達は、自由奔放な姿です。
それがまた、奇異感を増幅させています。
優雅な左幅。暴れん坊の右幅。
並べて一緒に見られることで、
お互いの魅力を引き出し合う一対です。
左幅上部の款記は
「九霞山樵写」
「九」が小さく、
「霞」が自由奔放な姿で、下部が「あ」的で右下に極端に下がるのは、
30才代後半から40才過ぎまでに多い書き方。
「池橆名印」朱文方印
「九霞山人」白文方印
共に、30才代後半に使われ始め、40才代で多く使われた印章。
同じ印材の両面で、ペアで捺されることが多いです。
国宝「楼閣山水図屏風」(東博蔵)にも、
重文「蘭亭曲水・龍山勝会(りょうざんしょうかい)図屏風」(静岡県立美術館蔵)にも、
この2印はペアで捺されています。
¥300000 ⇒40%Off ¥180000!
消費税・送料込
本紙 124 ×48,5㎝
軸装 185,5 ×64,5㎝
かなり大きいです
紙本墨画
箱無し
◇
◆5◆

◆竹図 小竹散人賛◆
真ん中に一節一筆ですーっと描かれた竹は少し撓(しな)っています。
葉が左から右へなびいていて、
強い風で幹が撓んでいるとわかります。
竹の葉を井桁(#)状に描くのは、
大雅の特徴の一つです。
葉っぱの先に、風で飛ばされる葉の軌道を描くのも、
大雅独特の竹の描き方です。
画世界の中で、さわさわと音を立てる葉を見事に視覚で表現しています。
紙の真ん中に
「三岳道者池無名寫」
と款記されていますね。
この位置は、竹が撓らずに真っ直ぐに立っていたら、
竹の幹で隠れてしまう場所です。
風で竹がギューッと撓(しな)った一瞬、
竹の後ろの落款が見える。
竹は実際に三次元に存在するもので、
落款は、画世界という二次元の世界にあるもの。
二つの次元が、
大雅の中で、関係性を持っています。
遊び心が発揮された作品です。
賛を書いたのは、
篠崎小竹(しのざきしょうちく/天明元・1781~嘉永4・1851)
儒者・漢学者・書家です。
大阪の私塾《梅花社》の二代目で、門弟が多く、
当時とても人気・権威がありました。
頼山陽との強いつながりも有名な方です。
小竹に賛を書いてもらうと作品にハクが付きましたので、
この大雅作品の所蔵者が、
後から、小竹に着賛してもらったのでしょう。
折れはございますが、きれいなコンデションです。
文人画らしい凝った造りの軸先が付けられています。
風の強い日の空を思わせる美しい色の中廻し裂と
常緑の竹の緑の天地裂、
画の動きを際立たせる貼り風帯。
センスの良い表具です。
「貨成」朱文方印
「大雅」白文長方印
紙 約113 × 26,7㎝
軸装 約183 × 36,1㎝
紙本墨画
時代箱
¥180,000 ⇒30%Off ¥126000!
消費税・送料込
◇
◇
他の作品で、「も少し安かったら手が届くのになぁ!」
の時は、
お気軽にご相談ください♪
お問い合わせをお待ちしております。
先行予約も受け付け中!
◆他の作品はこちらから◆
◆お問合せフォーム◆
電話/ 075-541-5128
4/24(木)~5/10(土)
11:00~18:00
会期中に休業日・留守の時間がございます。
4月24日(木) 11:00~18:00
25日(金) 11:00~18:00
26日(土) 11:00~18:00(留守の時間有)
27日(日) お休み
28日(月) 11:00~18:00
29日(火・祝) 11:00~18:00
30日(水) 11:00~18:00
5月1日(木) 11:00~18:00
2日(金) 11:00~18:00
3日(土・祝) 11:00~18:00
4日(日) 11:00~18:00(留守の時間有)
5日(月・祝) 11:00~18:00(留守の時間有)
6日(火・祝) 11:00~18:00
7日(水) 11:00~18:00
8日(木) 11:00~18:00
9日(金) 11:00~18:00
10(土) 11:00~18:00(留守の時間有)
今後予定変更の場合がございます。
恐れ入りますが、最新の営業日時をご参照ください。
骨董水妖
〒605-0089
京都市東山区古門前通大和大路東入元町367-4杉山ビル3F