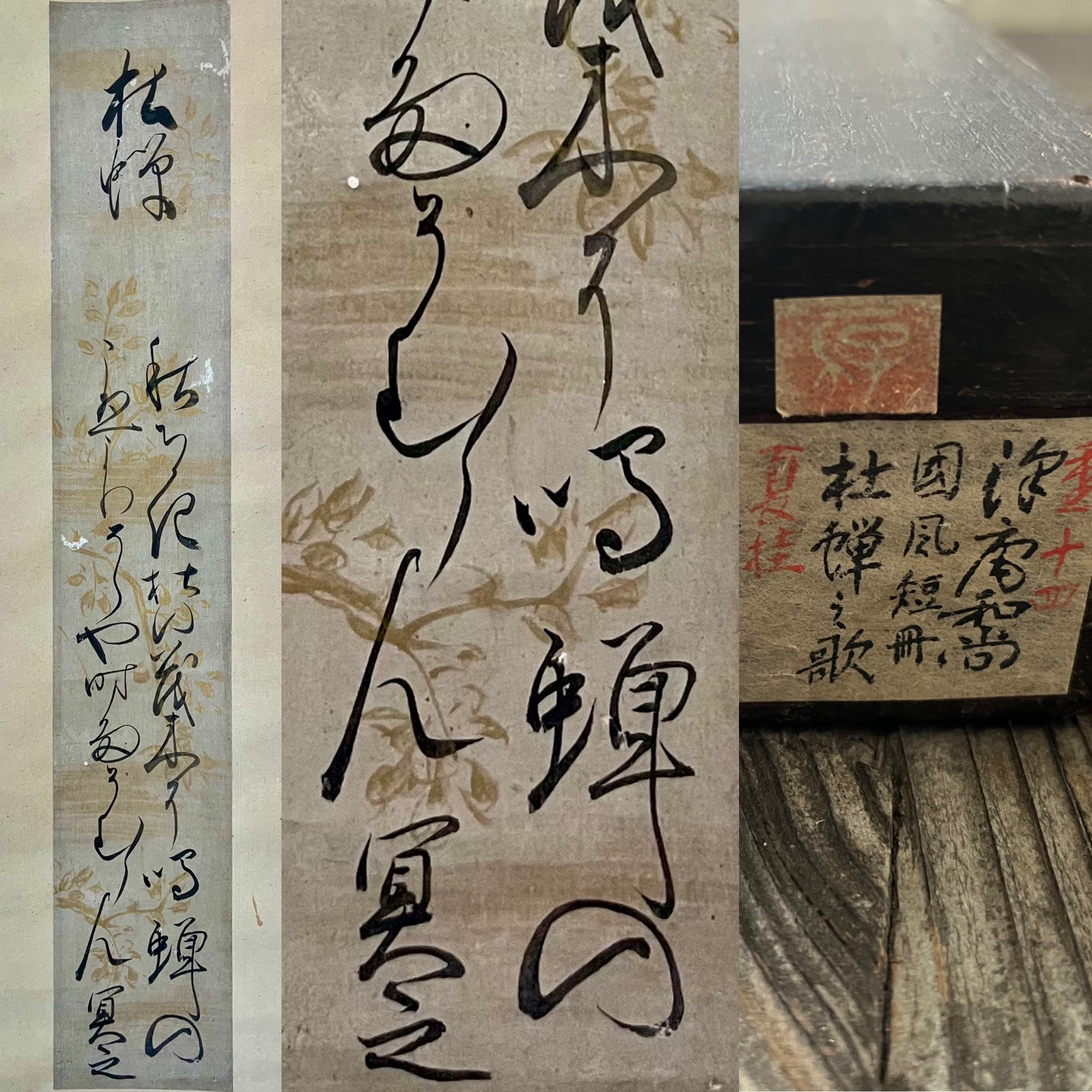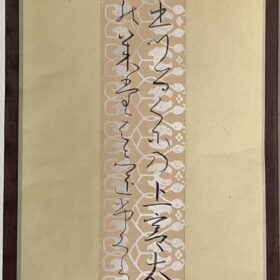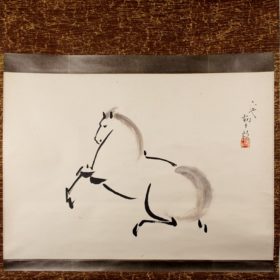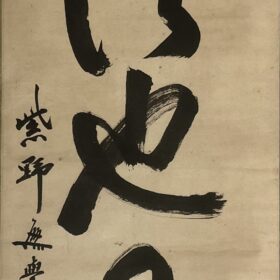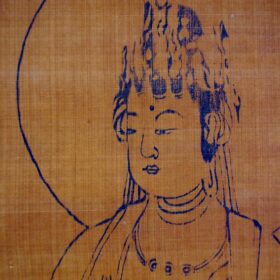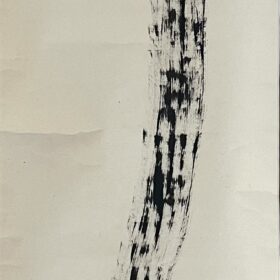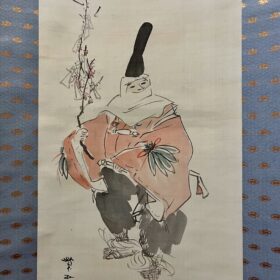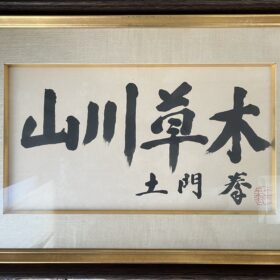短冊 約36 × 6㎝
軸装 約149 × 25,6㎝
紙本
□
澤庵宗彭
(たくあんそうほう)
天正元年(1573)~正保2年(1646)
たくあん漬けの澤庵さんです。
短冊の左下に書かれた「冥之」は、澤庵さんの字(あざな)です。
あまりにも有名すぎるため、本当に存在していたことが実感しにくい澤庵さん。
私にとっては、仮面ライダーと同じくらいの実在感でした。
でも実際に存在していました。
沢庵さんは桃山時代から江戸時代前期の人です。
江戸幕府成立まで、朝廷との関係で確立していた大徳寺・妙心寺の決まり事や朝廷の権利が、
江戸幕府確立後、将軍によってはく奪され、
それに正面から抵抗した澤庵ら高僧たちは、京都から遠い本州最北の地に流されます。
その後、許され京都に戻った後、
流配中に澤庵さんに帰依した将軍家光によって、
失われようとしていた秩序・権利は回復されます。
これがいわゆる「紫衣事件」。
私が学生の頃は歴史の教科書に載っていましたので、
沢庵さんは、教科書で見た有名人。
そんな歴史上の人物も、
書いたものが残っていると、実際に《いた》と、認識できます。
書いたものに直接触れると、
本当に生きていた人だったと、理屈抜きに感じられます。
□
杜蝉
秋ちか起杜の茂木耳鳴蝉の
こ○よ利曽良や時雨曽むらん
(秋ちかき 杜の茂木に鳴く蝉の)
(こえよりそらや 時雨そむらん)
□
金彩で下絵の描かれた、上質で格の高い短冊に書かれた一首。
このような様式で一番有名なのは、
同じ時代の、宗達下絵・光悦書の巻物でしょう。
夏から秋に季節が変わろうとしている
林で蝉の鳴く声がしているけど、
空は秋の色になろうとしている
蝉は土の中で育つ時間が長い割に、地上に出て成虫となって生を謳歌する時間が短い生き物。
しかも秋がすぐそこに見える夏の終わりを詠んだ歌です。
必ず終わりのある人生(life)。
そんなことは知らずに精いっぱい生きる蝉。
時間の終わりを告げる空模様の変化。
切ない内容ですが、澤庵さんの書き振りは、決してはかなくありません。
むしろ力強く、豪快です。
澤庵さんは、幕府に盾突いて、都から遥か遠い東北の地に流刑になっても、
その地の殿様を心酔させてしまったほどの禅僧。
その人間力が書に現れています。
「冥之」で、この作品の主が澤庵とわかる方は、
古典の心得のある方。
わかりやすいモノよりも、
鑑賞する側の素養を問われる作品を楽しめる方には、
価値ある作品です。
時代裂を使った格調高い表具。
本紙に虫穴がございます。
およそ400年前の作品です。
ご理解いただける方にはリーズナブルと存じます。
時代箱
《お問い合わせください》

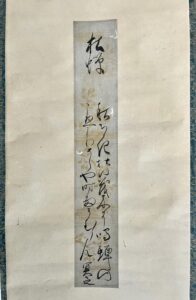
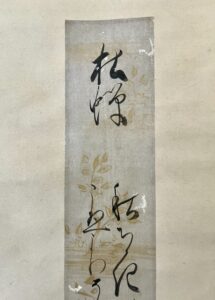
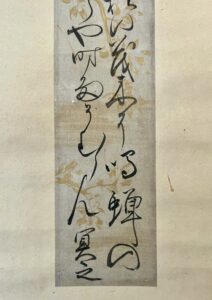
□





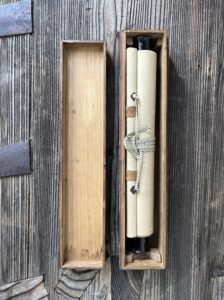
□