
◇茶箱
約10,5 ×17,8㎝
高さ 約11,8㎝
◇茶器
正玄作八代宗哲塗平棗
◇茶碗
祥瑞兎文
◇茶杓
飛来一閑作
◇茶巾筒
阿蘭陀写鳥花文
◇茶筅筒
飛来一閑作
◇帛紗
友湖製
◇茶筅立
四分一七宝透かし
◇菓子皿
◇香木
◇
 ◇祥瑞兎茶碗◇
◇祥瑞兎茶碗◇
高さ 約7,2㎝
口径 約8,8㎝
祥瑞は、明末・崇禎年間(1628~44)を中心に、
景徳鎮民窯で焼造された磁器。
日本からお茶道具として注文され、舶載されました。
典型的な祥瑞の茶碗は、口縁の内側にも文様が施されている場合が多いですが、
本作品は中は真っ白です。
また、この兎の文様は、祥瑞より一時代前の古染付に多い図柄です。
透明感に満ちた濃い染付のコバルトの発色や、菱型の窓の周りを埋め尽くす密な地紋、
裏の四角く囲われた銘、畳付きに見える胎土から判断し、
祥瑞といたしました。
形も、古染付の雲堂手の器形に近いです。
過渡期の作品と思われます。
生意気な表情で、脚を長くぶらっとさせた兎。
花菱形に抜かれた窓は、二重罫線で枠取りされ、
その外側は緻密な模様を埋め尽くし、更に木瓜型の枠が取られています。
枠と枠を繋ぐ格狭間の内には、瓔珞を逆さにしたような装飾が描かれます。
口縁から下に、一巻き区画を取って、
唐草を巻いています。
艶やかでピタッとする、最高の手触り。
口縁に虫食いがございます。
無疵



◇

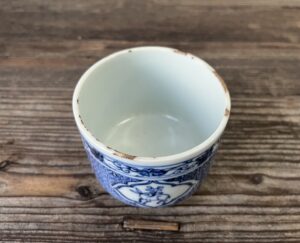
◇




◇
 ◇阿蘭陀写花鳥茶巾筒◇
◇阿蘭陀写花鳥茶巾筒◇
高さ 約6,4㎝
底径 約3,5㎝
乾山の作と考えられますが、銘はありません。
底の肌や少し見えている胎土は、乾山の阿蘭陀写し、印判で模様を施した角皿と同じ感じです。
葉を茂らせ、花の咲いた枝が周りをくるっと一周して、
顔の白い、羽根の青い鳥が止まっています。
無疵



◇



◇
 ◇正玄作 八代宗哲塗平棗◇
◇正玄作 八代宗哲塗平棗◇
高さ 約5,6㎝
胴径 約7,3㎝
千家十職の竹細工師・柄杓師の黒田正玄が竹で作り、
同じく千家の職方、塗師・中村宗哲が漆を施した平棗。
底裏に「正玄」の小判型の印が刻され、
「哲」と針彫りされています。
八代宗哲(文政11/1828~明治17/1884)の銘の姿です。
同時代の正玄は十代と考えられます。
竹の節を、蓋の上面と身の底に使った平棗。
竹は木材と違って素材に制約が多く、
肉も薄く、棗の上下のアールをつけるのは超絶な技術。
また、節の部分の自然で激しい凹凸によって、
程化された漆に濃淡が強く現れ、
原野のような力のある景色を見せています。
竹の繊維が水平に切られたことでできる、緻密なぽつぽつ模様も、
他の材では決して現れない神秘的な表情です。
派手な見映えではないだけに、これを取り合わせた旧蔵者の卓越したセンスが現れています。




身内/ 蓋裏


裏/ 銘部分拡大



同時に製作されたと思われる竹製塗木皿

棗には収まりません
◇
 ◇茶杓◇
◇茶杓◇
飛来一閑作
長さ 約4,4㎝



裏に「飛」の朱漆銘有り

◇
 ◇茶筅筒◇
◇茶筅筒◇
飛来一閑作
高さ 約9,1㎝
胴径 約4㎝
「飛」の朱漆銘有り。
一本紐を巻いたように、ほんのわずかな胴締めが抜群なデザインです。

◇
 ◇帛紗◇
◇帛紗◇
友湖製
約12㎝四方
折って見える側に福寿草の織模様
生地が薄いです。

◇
 ◇茶筅立◇
◇茶筅立◇
四分一七宝透かし
高さ 約2,5㎝
底径一辺 約2,7㎝
四分一(しぶいち)は銀に他の金属を混ぜた合金です。
微妙な美しい色が人の心を掴んで離さず、
江戸時代から明治の金工に於いて、最高級品に好んで使われました。
画像で、軸の上半分と下半分の色が違うことがご覧いただけると思います。
底部分に魚々子模様が鏨で施されています。
七宝模様の周囲の丸は正円ではなく、手作業で作られたことがはっきり見て取れます。
小さな道具にまで、手抜きのない仕事です。


真上から/下から
◇


茶箱としては小さめです。
茶通箱より少しだけ大きい感じです。
蓋上は気持ち甲盛された手の込んだ造形。
お茶碗にあまりにピッタリで、お茶碗のために誂えたという印象です。
あまりに上等な茶碗と茶巾筒が手に入ったために、
他の道具は、千家十職の職方で誂え、極上にして目立たない品々で組んだ。
そんな印象です。
比類のない素晴らしいセンスと存じます。
《お問い合わせください》
 香木も入っていました
香木も入っていました




□


 裏にちょっとだけ虫食い有り
裏にちょっとだけ虫食い有り









