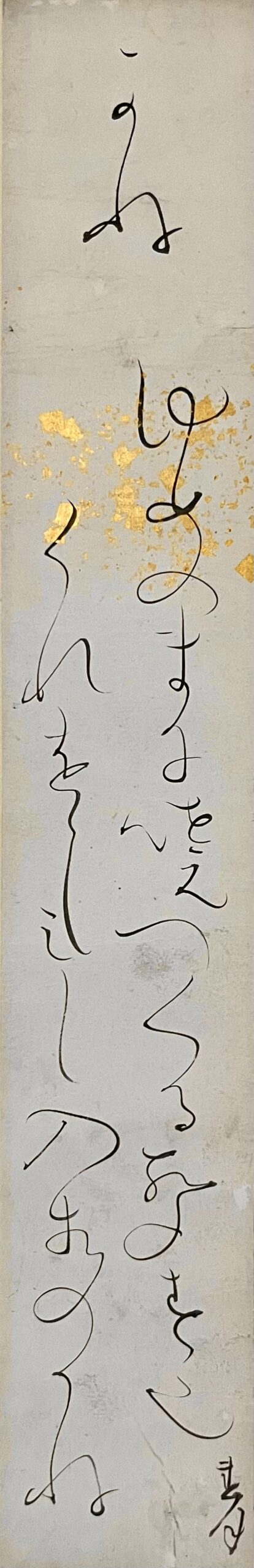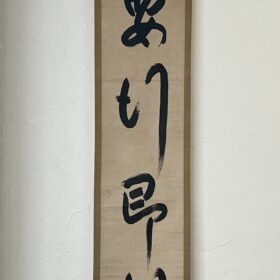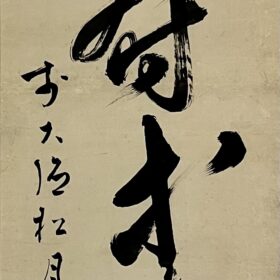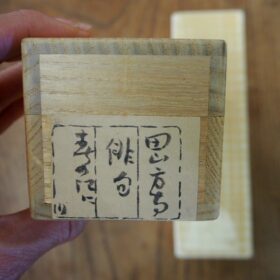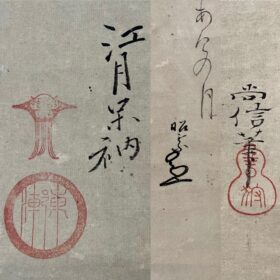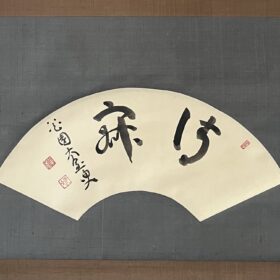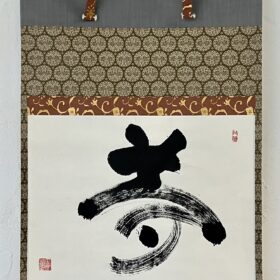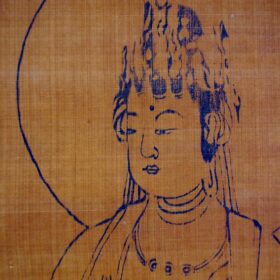本紙短冊 36,5 ×6㎝
軸装 137 ×26,4㎝
紙本
□
大田垣蓮月
(おおたがきれんげつ)
寛政3(1791)~明治8(1875)
生まれてすぐに京都知恩院門跡勤士の養女になり
同家の養子と結婚→死別。
次に同家の養子となった人と結婚→死別。
その後仏門に入ったのだそうです。
その時32歳。
想像を絶する人生です。
個人の人生よりも《家》の存続・繁栄に、圧倒的に重きが置かれていた時代に、
自分に課せられた運命を全うしようと身を尽くす女性。
養父の死後、岡崎に移り住み、陶芸で生計を立てました。
歌人としても高く評価されています。
青年期の冨岡鉄斎を侍童として共に暮らし、鉄斎に大きな影響を与えました。
そのため、鉄斎の画に蓮月の一句の合作も多く作られています。
□
かね
ゆめのま耳 暁つくる聲春也
くれをゝしミし 入相のかね 蓮月
(夢の間に 暁告ぐる声すなり)
(暮を惜しみし 入相の鐘)
□
筆の運びに滞りの全くない、美しいお手。
「ゆめの」はくるくると一筆。
ちょうど、短冊の金の切箔装飾のある部分の上に書かれ、
「ゆめ」が感覚的に伝わります。
平安時代からずっと、
文字は意味を伝える記号としてだけでなく、
視覚的に美しいことが、一つの最も重要なポイントでした。
現在も、どんなフォントで書かれているか?で、
伝わり方は全く違いますね。
蓮月の文字は、派手な動きではなく、
よどみない連綿の中に完成されています。
表具される前に、短冊単体として長く保管されていた感じです。
汚れや皺がございます。
コンデションは画象でご確認ください。
古裂を使った格調高い軸装です。
無地誂え箱
¥45000
消費税・送料込

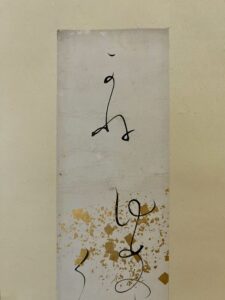
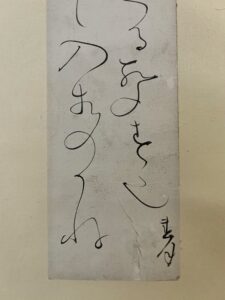
□



□




□