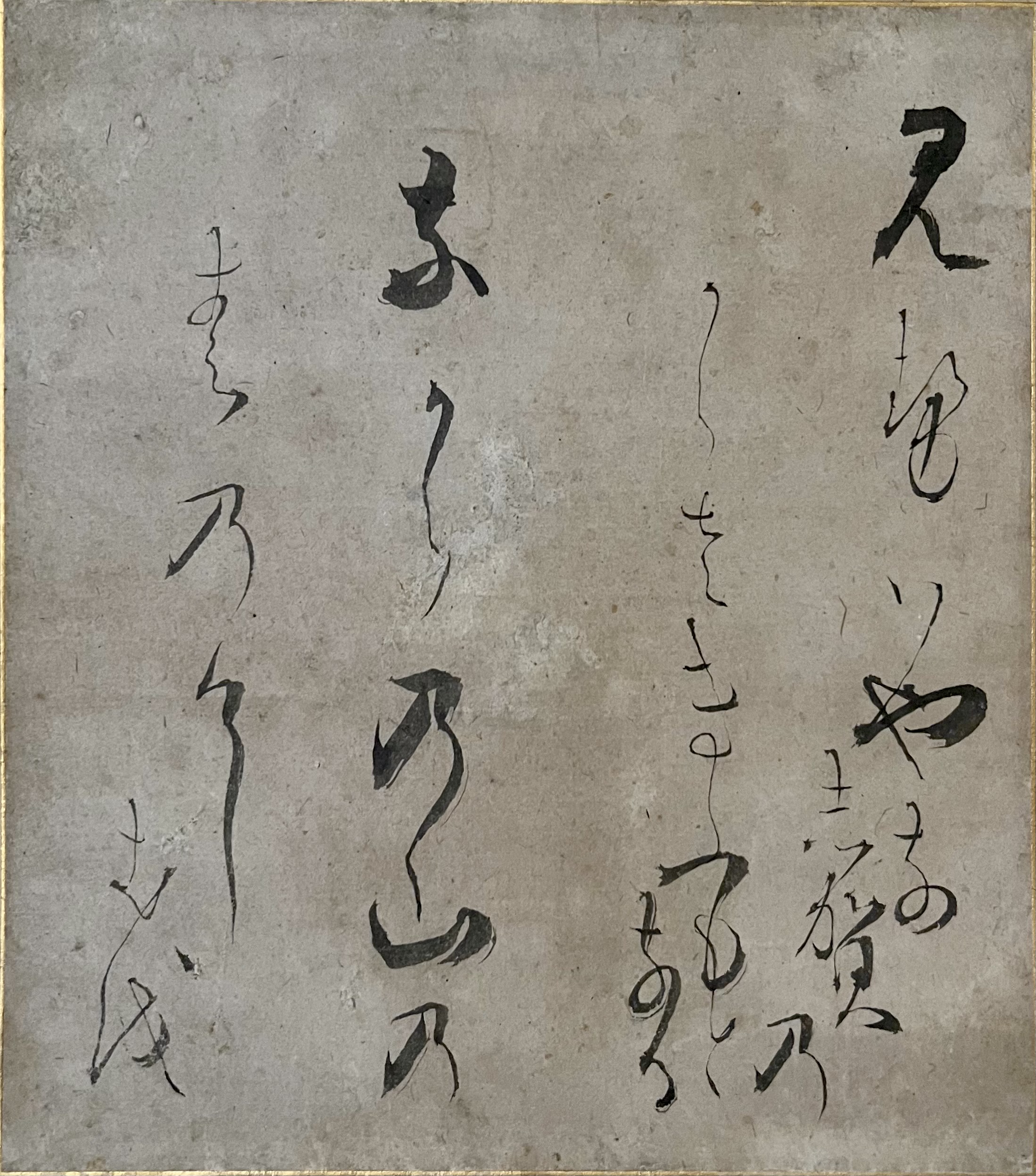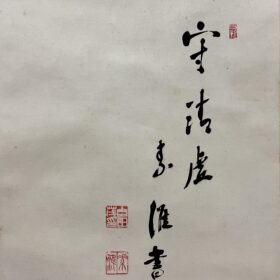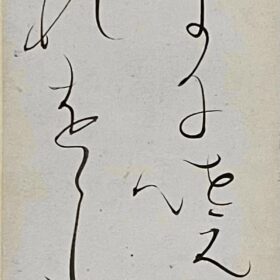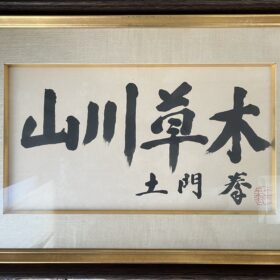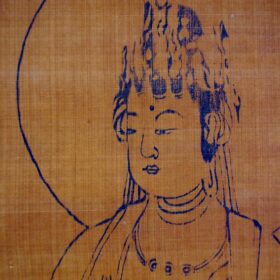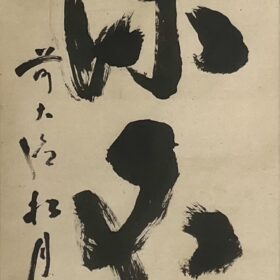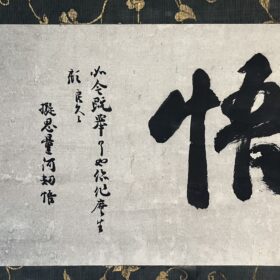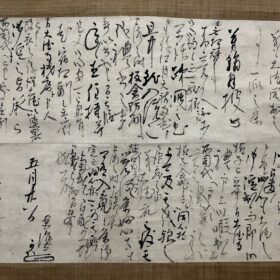本紙 約19,9 ×17,7㎝
軸装 約134,5 ×30㎝
紙本
□
本阿弥光悦
(ほんあみこうえつ)
永禄元年(1558)~寛永14年(1637)
桃山~江戸時代初期の文化芸術の最高峰人物。
書は「寛永の三筆」の一人と称され、
俵屋宗達下絵・光悦書のコラボ作品は、
琳派芸術の金字塔として君臨しています。
極端な丸い造形に、鮑を螺鈿・鉛板を大胆に貼り、
厚く盛った金銀蒔絵の「光琳蒔絵」の漆芸作品、
独特な造形美の陶芸作品など、
多方面に、圧倒的斬新で大胆な作品を残しました。
その後の時代の文化芸術への影響の計り知れないアーティストです。
国宝・重要文化財に指定された作品が、
非常に多いのです。
□
見勢ハや奈 /みせばやな
志賀乃 /しか(が)の
からさきふもと
なる
奈から乃山乃 /なか(が)らの山の
春乃介し /春のけし
支越 /きを
□
滋賀の唐崎の麓、長等(ながら)は、
平安時代の武将・平忠度(たいらのただのり)が歌に詠んだほど昔からの桜の名所。
慈円(1155~1225/平安末から鎌倉初)の詠んだ歌で、
新古今和歌集に勅撰されています。
見せたいなぁ!
滋賀の唐崎の麓の、この有名な長等の桜の美しい景色を。
長等公園は今も桜の名所。
800年も前から、人々が桜を楽しんでいたんですね。
桜といえばの西行さんの次に、
慈円の歌はたくさんの新古今和歌集に入っているそうです。
光悦の時代には、
古典として常識だったのでしょう。
肥痩の極端な、光悦特有のお手。
横画と右上から左下に降ろされる筆が極太で、
縦線はほとんど毛の一本で紙に触れているといった様子。
「ふもと」の部分の
上に行ったり下にいったりの連綿の所がカッコイイ!
「なる」の「る」はほとんどミジンコみたいな姿。
上の「な」の丸まりとの調和、
そのあたりの文字の詰まった感じが絶妙です。
本作品は、間違いなく光悦の筆ですが、款(サイン)がありません。
新古今和歌集の歌を書いた巻物の断簡を軸装したと推測されます。
本紙の周りに極く細い金の線が巡らされ、
一文字・風帯は緑地唐花古金襴、
中廻しも唐花唐草古金襴。
格調高い軸装です。
本紙に、虫による傷みを修復した痕跡がございますが、
悪くないコンディションです。
古筆極札有
冷泉為紀(れいぜいためもと/1854~1905)極め箱
¥220000
消費税・送料込




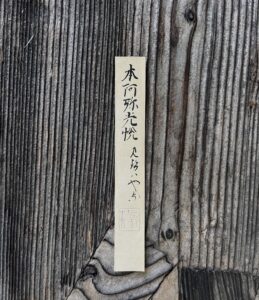

古筆極め札表裏(包紙無)


箱書き表「光悦四季紙 見勢者奈や」/ 裏「明治卅八年五月 冷泉為紀花押」


几帳面を施した箱 両面