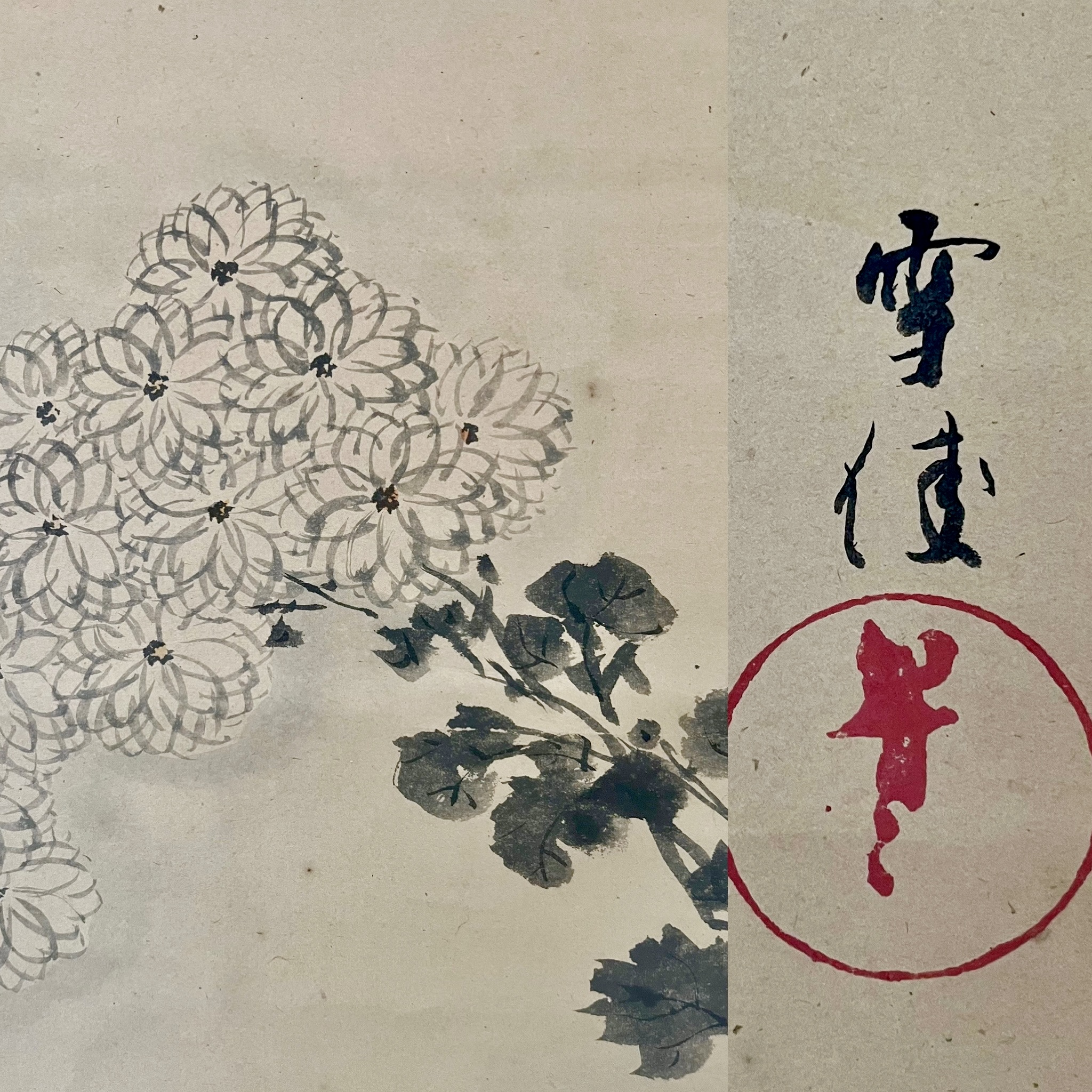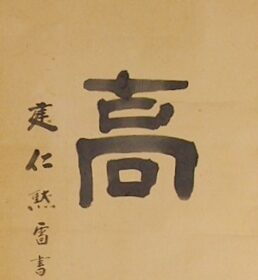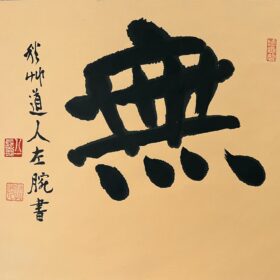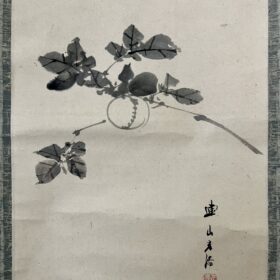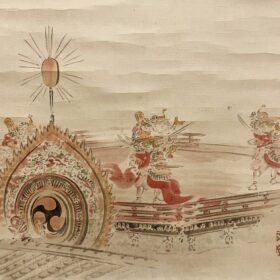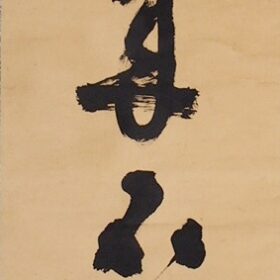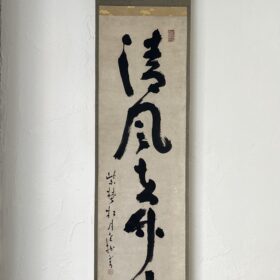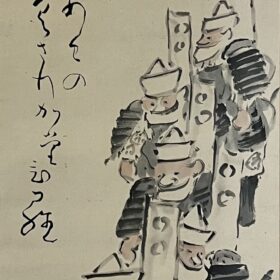本紙 約132×29,7㎝
軸装 約195 ×35㎝
紙本淡彩
□
神坂雪佳
(かみさかせっか)
慶應2年(1866)~昭和17年(1942)
京都生まれ。
四条派の日本画を学び、装飾芸術の道に。
琳派に傾倒し、琳派の技法を取り入れたモダンな作品の図案を手がけました。
装飾芸術文化を社会に確立させた立役者です。
□
この作品を一目見て、
雪佳の才能の凄さを思わない人はいないでしょう。
菊は地面から高く伸びて、一度画面からすれすれに外れてしまいます。
ギューッと花の重みでしなって又画面に戻ります。
空間を切り取って、芸術とする見事な手法!
痺れる構図です。
没骨で描かれた重なる葉や茎たち。
確かなデッサン力に基づく迷いのない筆。
新鮮な菊の香りが漂うようです。
花弁を重ねる白菊の周りには、薄墨が施され、
花芯にだけオレンジ色が差されて、花の白さが際立ちます。
素晴らしいセンス!
お気づきでしょうか、
葉茎の姿や生態はリアルでありながら、
花はみんなこっちを向いています!
虚実が、雪佳の手によって見事にここに美しい姿を顕しています。
本紙に折れ、わずかな汚れがございます。
画像でコンディションをご確認ください。
雪佳が原画を描き、明治42年~43年に芸艸堂から出版された木版美術本「百々世草」には、
本作品が基になったであろう肉筆原画「ももよ草」があり、
2006年の「神坂雪佳展」図録に掲載されています。(107頁)
「雪佳」の落款は、大正末くらいから丸みを帯び、肥痩のある琳派的な姿ですが、
明治までは直線的です。本作品の落款の姿は、
細身美術館ご所蔵の、正面向きの金魚の絵(明治末頃)の落款に近いです。
「百々世草」の出版時期と合わせて、
明治期、比較的若い時代の作品でしょう。
無地箱
《お問い合わせください》


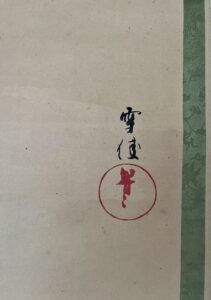

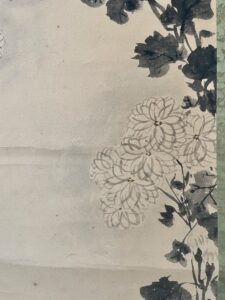

□



□
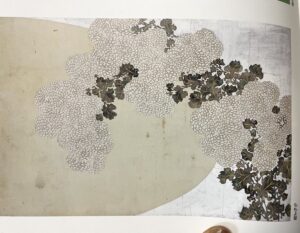
「神坂雪佳展」図録2006年より転載
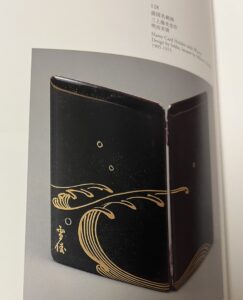
「神坂雪佳」展図録2003年より転載
明治末ごろの雪佳下絵作品