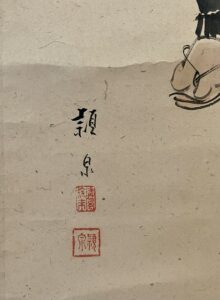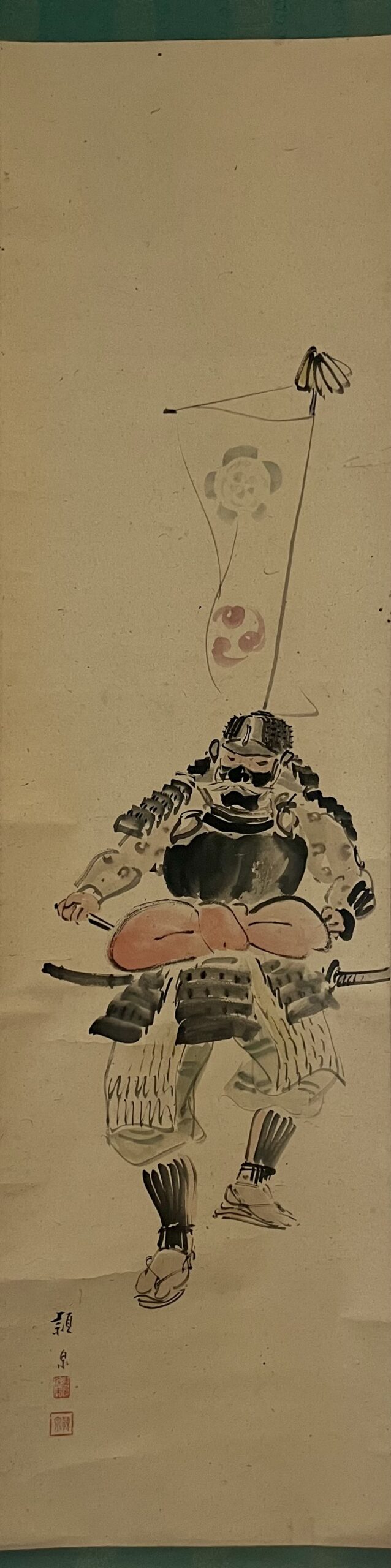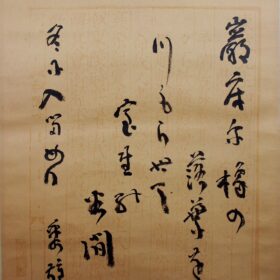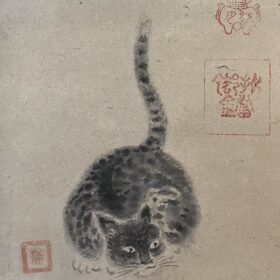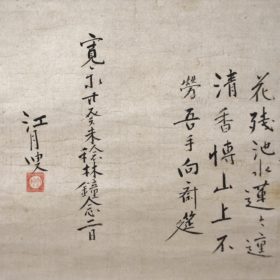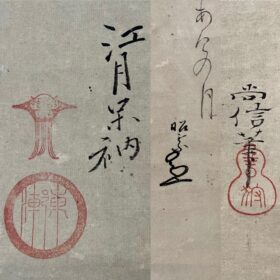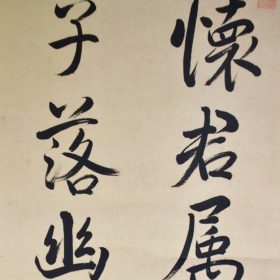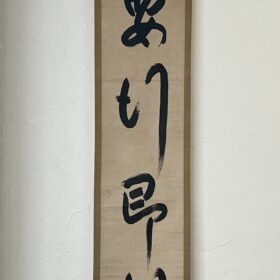本紙 109,6 ×29,4㎝
軸装 188 ×32,2㎝
紙本着色
□
作者の頴泉については、名前が「修」であること以外の仔細は不明です。
京都国立博物館所に作品が10点所蔵されていて、
いずれも名品の摸本、写し作品です。
制作年がわかる作品は、
聖徳太子尊像(原本御物・明治40年)
伊藤若冲肖像摸本(原本小保田米僊筆・昭和丁卯/2年)
抱一上人法服像模写(原本伝酒井鶯蒲筆・昭和5年)
僧明兆像模写(原本住吉廣行模写東福寺・昭和5年)
芦雪肖像(昭和丁丑/12年)
明治~昭和初期にかけて活動された絵師のようです。
上御霊神社に奉納された絵馬にも名前がある、とした資料もありました。
上記作品の中で、
伊藤若冲肖像摸本のオリジナル作品は、
若冲の肖像画として一番有名な明治18年に久保田米僊の描いた相国寺ご所蔵作品です。
見覚えのある方も多いでしょう。
御物や格式高い寺院の作品を写せた頴泉は、
非常に高いレベルの絵師であったことが推測されます。
鳥羽僧正筆 鳥獣戯画の巻物の摸本も制作しています。
□
弦召(つるめそ)は、
祇園祭の神幸祭(7/17に三基の御神輿が八坂神社から四条の御旅所まで巡行)の時の、
建仁寺の南西付近・弓矢町からの供奉で、
警護と露払いとして、中御座神輿の先導であったそうです。
鎧を着けた武者姿の、
江戸時代の祇園祭の代表的な風物詩でした。
夏の一番暑い盛りに、
重く風通しの無い鎧を着けて、歩いて行列しなければならない、
もの凄くキツい役割であったこと、
汗で傷んだ鎧の修復にお金がかかることなどから、
昭和四十九年を最後に、
行列から姿を消した幻の役柄でしたが
本年・平成7年に弓矢町の武者行列が、神幸祭・還幸祭で復活されます。
今まで見た弦召の絵は、
皆面頬(めんぽう)だけて、兜を被っていませんでしたが、
この作品では、とげとげの霰のある兜に、腰に太いリボン状の紐を巻いている姿。
弓矢町の公式サイトに掲載された「弓矢町武者神役」のいでたちに近いです。
《参考作品》