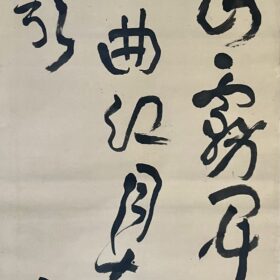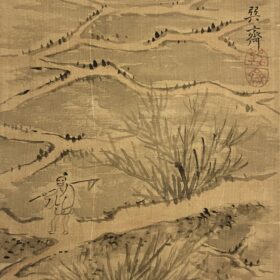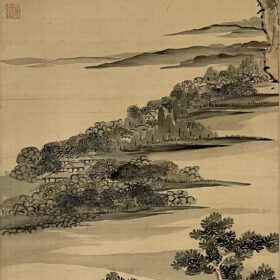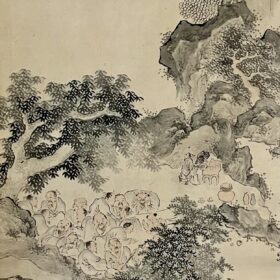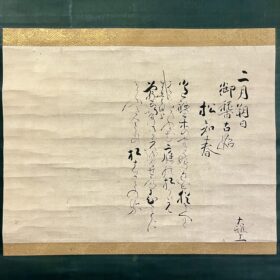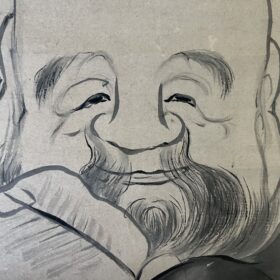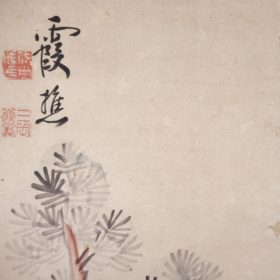寿老図
本紙 約115,2 ×45,4㎝
軸装 約204 ×58㎝
水亭舟翠図
本紙 約115 ×45,4㎝
軸装 約204 ×57,4㎝
紙本淡彩
□
もの凄い存在感の寿老人です。
頭の長いこの神様は、
《福禄寿》と《寿老人》の二人の神様が一体となった神様。
《福禄寿》は、もともと中国では《福星》《禄星》《寿星》の3つの星が神格化し、
一体となった神様で「三星」とも呼ばれました。
長すぎる頭と長い髭で描かれます。
3つの星の内の《寿星》が、
天下泰平の時に現れるといわれる南極老人星の化身《寿老人》として日本に伝わったらしい。
大雅はこの神様を「南極寿星」としています。
大好きだったのでしょう。
池大雅作品集(中央公論美術出版/昭和35年)には8作品所載されています。
本作品の寿老人は、今までに見た大雅の寿老人の中でも特に凄い!
115㎝の画面の中で、身長80㎝。
横幅もギリギリまで大きく描かれます。
なんといってもその表情!
大きな鼻の両脇の瞳はつぶらですが、強烈な眼力、
見る者の目線を釘付けにし、ロックオンされて胸を射抜かれてしまう。
大きく口角の上がった口元。
吹きあがる噴水のような豊かな髭。
この世のモノならぬ、異界の存在感。
顔・頭・手の肌部分に代赭(朱)が施され、とっても生々しい。
手に持っているのは、寿命が書かれた巻物です。
体の前に垂れた帯がなびいていて、
右脚が前に出て動いていることがわかります。
ぬーっと、見る者に近づいているんです!
巻物の軸先や紐に代赭、腰ひもに黄色と少し藍色が加えられています。
大雅の描く神様は、高いところから神々しく降臨される存在ではありません。
気が付いたら傍にいて、
人智の及ばぬ力で、見る者に寄り添い、見守り幸せにしてくれる、
そんな感じです。
□
もう一幅の山水画のタイトルを「水亭舟翠」としました。
出光美術館ご所蔵の重要文化財
《十二ヶ月離合山水図屏風》は、大雅47才の傑作。
大変有名な作品ですのでご存じの方も多いことでしょう。
この屏風は、それぞれ独立した山水画としても、
12幅全体を大きな画面としても楽しめるスタイルで、
各幅それぞれに、四文字のタイトルが大雅の筆によって書かれています。
本作品は、その中の一幅「水亭舟翠」に、構図がよく似ています。
ただ、その大雅の筆による画題の一文字が解読できなかったので、
もしかしたら間違っているかもしれません。
画面手前には、松をはじめとする様々な樹々が潤った筆で描かれます。
その墨の一筆一筆は、ただの線・点・○ではなく、
葉の一枚一枚を生き生きと写しています。
所々墨の色が濃い。
なんて美しい描写だろう。
葉を揺らす気持ちのいい風や、緑の香りまで伝わってきます。
一番手前の右手の木陰、水に浮かべられた舟が繋がれていますね。
この水辺は、遠景の遥々とした水辺へと繋がっています。
気持ちの良い世界だなぁ。
大雅の画世界の住人に、知らぬ間になってしまいます。
水景を見下ろす岩上の素朴な建物、
背後に巨岩の山が迫っています。
山の輪郭は、なんの迷いも無駄もない筆で大胆に引かれています。
素晴らしい筆致です。
この幅はコンデションが良くありません。
全体的に表面に多く欠損がございます。
古書画を扱う業者は、「虫が舐めた」と表現します。
「虫が喰った」ほど、深くはっきりと紙が亡くなっているのではなく、
「舐めてなくなった」ように表面がなくなっている状態です。
運よく、手前の樹々部分は欠損が少なく、
上半分の難が多いです。
他に傷み、汚れも多いです。
印章〈遵生〉朱文長方印は、30才代後期~生涯使われた印章。
〈池橆名印〉白文方印(左上が丸い)は、
30才代末から使われ始め、重要文化財「五君咏図」、出光美術館ご所蔵「瓢鮎図」など、
50才代最晩年まで使用された印章です。
この印影は、とてもよく似た左上が四角い印章もあり、
図版だと判断しにくいのですが、上記の作品は確実です。
40才代後半の作品でしょう。
本作品には款記はありません。
元々屏風に貼られていた作品の内2幅が独立して軸装されたと考えられます。
寿老人の軸は、本紙に大きな折れがございます。
他に汚れや欠損部分もございます。
非常にリーズナブルでございます。
ご確認ください。
時代箱
¥120000
消費税・送料込


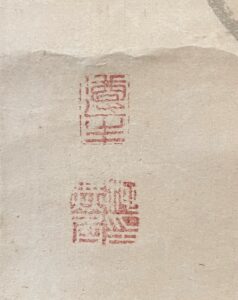
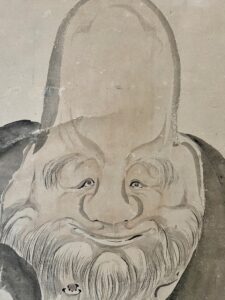
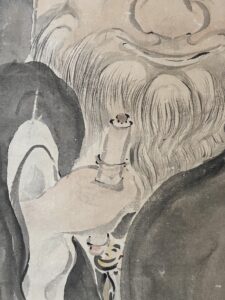
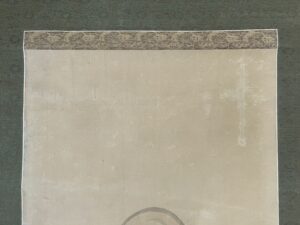
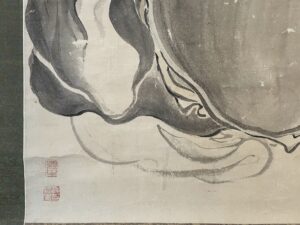
□



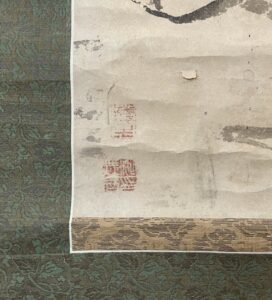

□





□
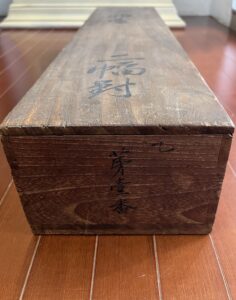
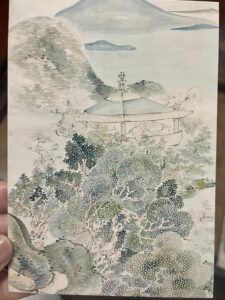

左が出光美術館ご所蔵の重要文化財《十二ヶ月離合山水図屏風》「水亭舟翠」(部分)のはがき/右は本作品
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。