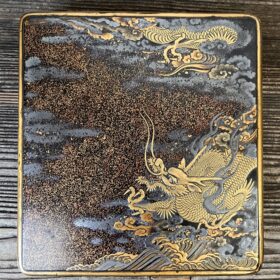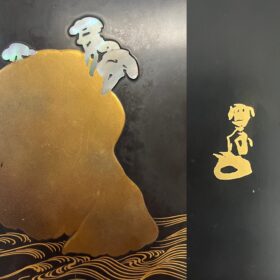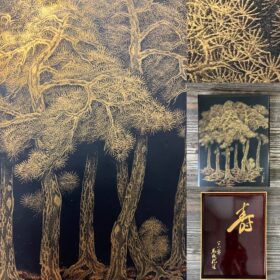縦 約22,8㎝
横 約20,8㎝
高さ 約5,3㎝
桃山~江戸時代初期
□
硯箱の一番古いのは平安時代末の《州浜鵜螺鈿硯箱》で、
平安時代の硯箱は確か一つだけです。
白洲正子さんのご所蔵で、その後、京都の古美術商の方のところへ。
重要文化財です。
蓋表(甲)が膨らむ甲盛(こうもり)、
側面が膨らむ胴張(どうばり)の形で、
縦横の長さが同じ方形で、入隅の形なところは、
春日大社の本宮御料古神宝類の一つ、櫛箱(国宝)に通じています。
甲盛・胴張の造形は、真っすぐな線で形を成す箱に比べ、
制作技術が、圧倒的に難しい。
アールを描いた辺の箱は、職人の高度な技術力を必要とし、格段に手間のかかる形です。
本作品は、方形に近い長方形、角丸被蓋(かぶせぶた)造、甲盛・胴張。
慶長二年(1597)の銘のある、北野天満宮の硯箱もこの形です。
江戸時代に人気のあった硯箱の形の一つです。
◇
蓋甲は、荒い梨地に、左手の重ねられた土坡に満開の桜が描かれます。
桜の花びらはみんな正面を向き、厚手の銀箔が貼られ非常に装飾的。
花に比べて樹が小さく描かれます。
葉は黒漆に輪郭と葉脈が金ですが、
これは金蒔絵の金が擦れてなくなったものと思われます。
アールを重ねた土坡の稜線は金銀の切金(きりかね)が贅沢に敷き詰められて豪華です。
土坡の下の水辺は細線を重ねた研ぎ出し蒔絵。
圧倒的な、素晴らしい蒔絵技術です!
対岸には鋭利な形の土坡があり、
薄い銀板を貼った橋が掛けられています。
よくよく見ると、その銀の輪郭が極く極く細く表されています。
凄い技!截金のようです。
これでもか、これでもかと、装飾技法を重ねています。
桃山時代の、自由で突き抜けた感覚が、一目で心を掴む抜群の意匠。
最高です。
アールのかかった側面に画面は連続しています。
更に身の側面に連続していきます。
◇
身は、左に縁に金を蒔いた硯と丸型の黄銅の水滴を置き、
右側に懸子を備えます。
いずれも梨地が施されます。
懸子には、蓋表の図が連続するように、
金銀切金を敷き詰めた金蒔絵の土坡から、満開の桜が描かれます。
◇
蓋裏がこれが又素晴らしい!
画面いっぱいに大きな孔雀がすっかり金で描かれます。
その胸は薄肉金高蒔絵に銀金貝をほぼ規則的に施します。
ほっぺの辺りだけ更に高く盛って、金切金(きんきりかね)を密に施し変化をつけています。
羽部分は、粉感の残る金粉を厚く蒔き、
尾羽の羽根の毛一本一本を付け描きで表現し、
羽根の芯は螺鈿が細く貼られ、飾り羽にも螺鈿が装飾されます。
踏ん張った脚の描写は妙にリアル。
足元は際を斜めに切った動きのある、流水にも見える広い金の台地。
輪郭には金銀切金が贅沢に用いられ、豪華で優美。
非常に絵画的です。
こんなに繊細際まる造形でありながら、器体に瑕疵はございません。
数百年を経ても狂わない材を用いて、抜群の技巧をして、
上質な漆で制作されているのでしょう。
制作に、時間もお金も惜しみなく注がれた逸品、
ミュージアムピースといっても過言ではございません。
蓋表に小疵、銀箔の擦れ、切金の剥落
経年による断紋などはございますが、
抜群のコンディションです。
漆拭時代箱
《お問い合わせください》




左下に小疵/ 銀板の捲れ部分
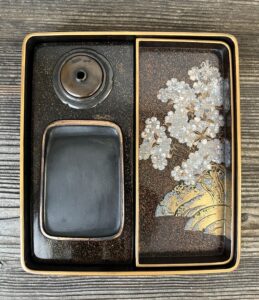

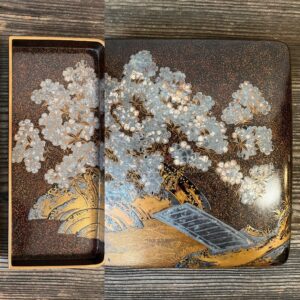
 蓋裏
蓋裏


□


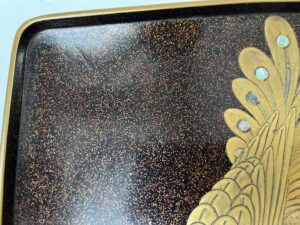
蓋裏仔細


 内容品裏面
内容品裏面


硯・水注/懸子側面




身側面四方

身裏面
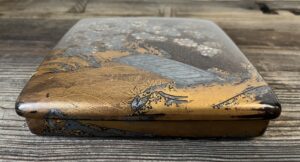
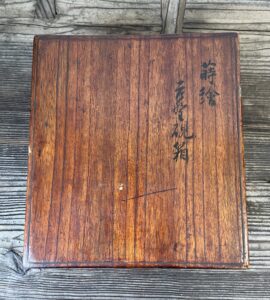

箱蓋表/ 箱の一部に一度外れた痕跡がございます(向こう側の面)
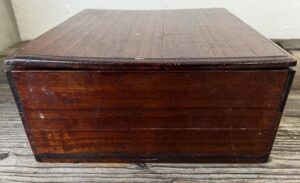
蓋がやや反っています
 箱蓋裏
箱蓋裏
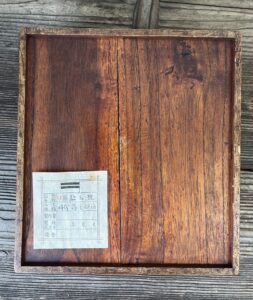
箱底裏