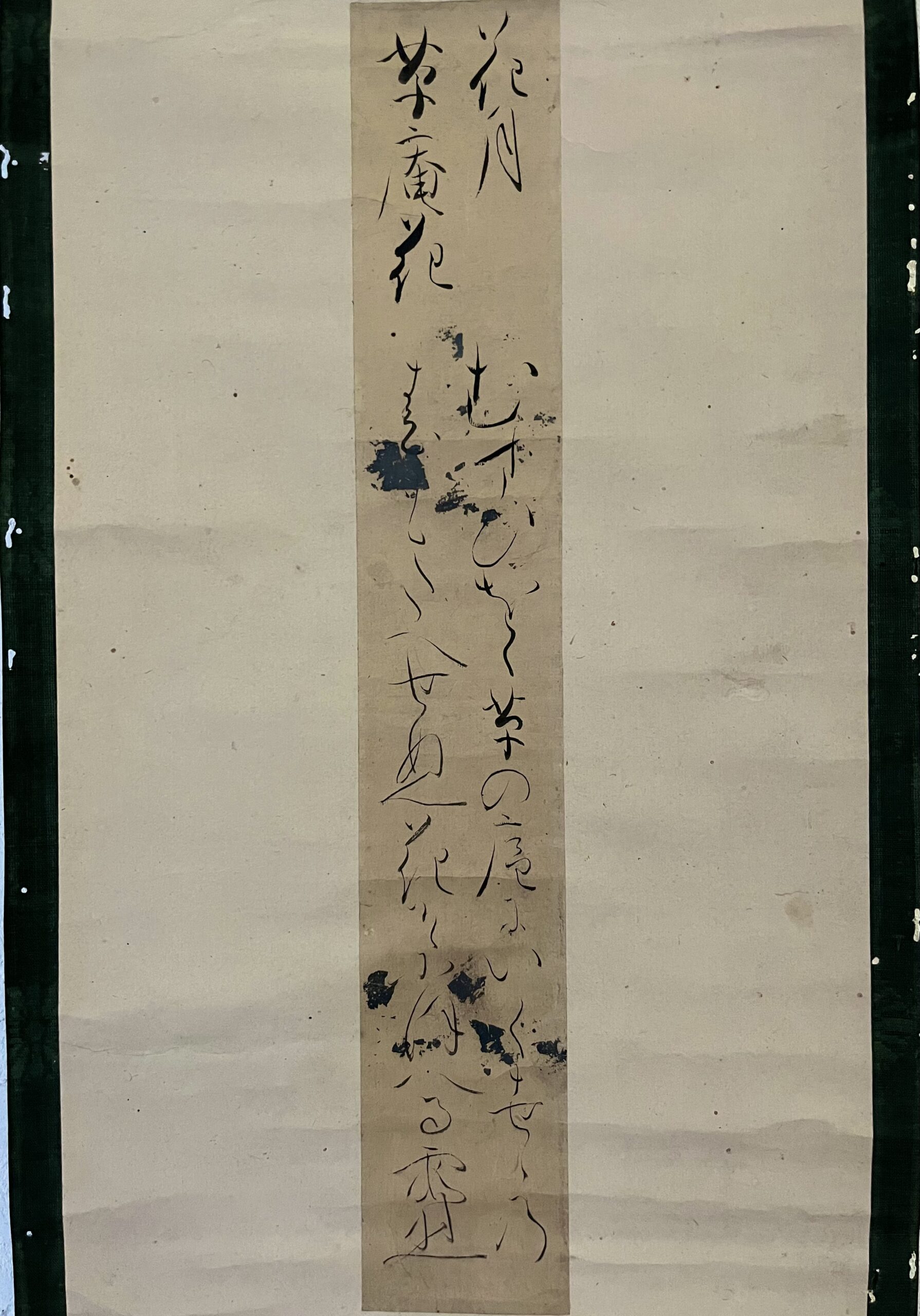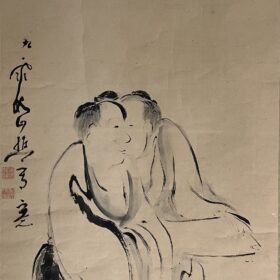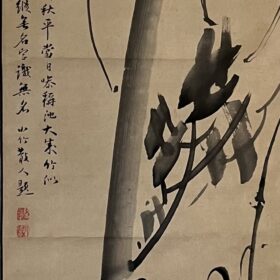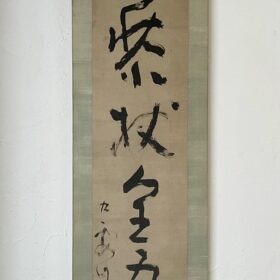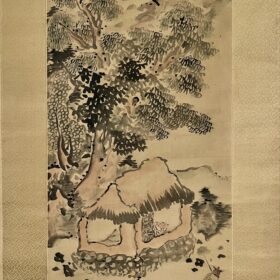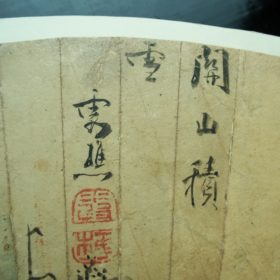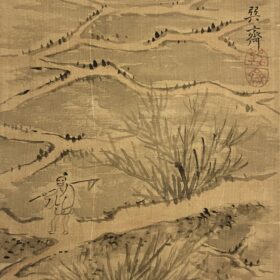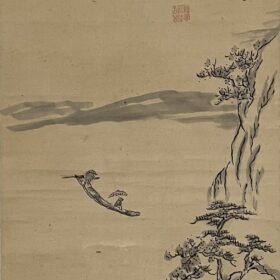本紙 36,4 × 5,8㎝
軸装 161,5 × 24,8㎝
紙本
□
花月草庵花
むすびをく 草の庵にいく世ゝ乃
春もたへせぬ花そにほへる 霞樵
□
大雅特有の文字姿。
和歌に相応しい非常に美しい書姿です。
この一句は、大雅のお気に入りの一句であったらしく、
同じ歌の短冊が、池大雅作品集(中央公論美術出版/昭和35)に
所載されています。(作品№677)
大雅は、妻・玉瀾と一緒に、冷泉家で歌の手ほどきを受けています。
玉瀾は、本名・町。
玉瀾の家は祇園の茶屋で、祖母の梶の代から冷泉家に歌を学んだ文芸で高名な一家。
梶さんも、母の百合も、
大変な美人で、歌集を出版したほど名高かったんです。
伴蒿蹊著「近世畸人伝」(寛政2年/1790)には、
二人が冷泉為村に招かれて参上し、歌を学んだ、とあります。
ちなみに、
初めて行ったとき、玉瀾の名前が高貴そうなので、
女房たちが玉瀾の来るのを楽しみに待っていたところ、
玉瀾は糊の良く効いた綿衣を着て、魚籠を下げてやってきて、
(つまりは、全然高貴な風体でなく、)
女房達を大いに驚かせた、
とも書かれています。
□
短冊の濃いグレーに見える部分は、銀箔です。
本銀は、経年で酸化して黒く変色するんです。
高級な料紙です。
軸装は虫食いが多く、
台紙の上部分に、広範囲な修復痕、下部には虫穴、折れがございますが、
短冊本紙は、折れが少しある程度です。
時代箱
箱にも、激しく虫食い跡がございます。
蓋は後補の可能性がございます。
塗りの軸先にも剝げがございます。
画像でご確認ください。
¥110,000
消費税・送料込
(税抜き ¥100,000)
![]()



台紙補修部分
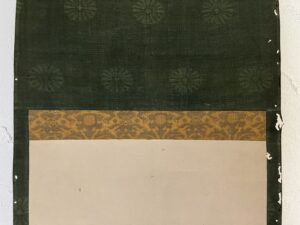
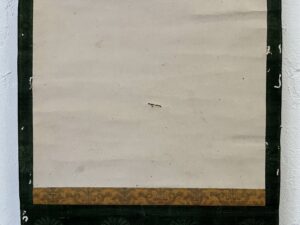
台紙虫穴
 軸塗り塗りの傷み
軸塗り塗りの傷み
 箱の表・左・裏・右
箱の表・左・裏・右

 軸装裏側
軸装裏側
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら
一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、
その作品を愛藏されていました。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。
□ □ □