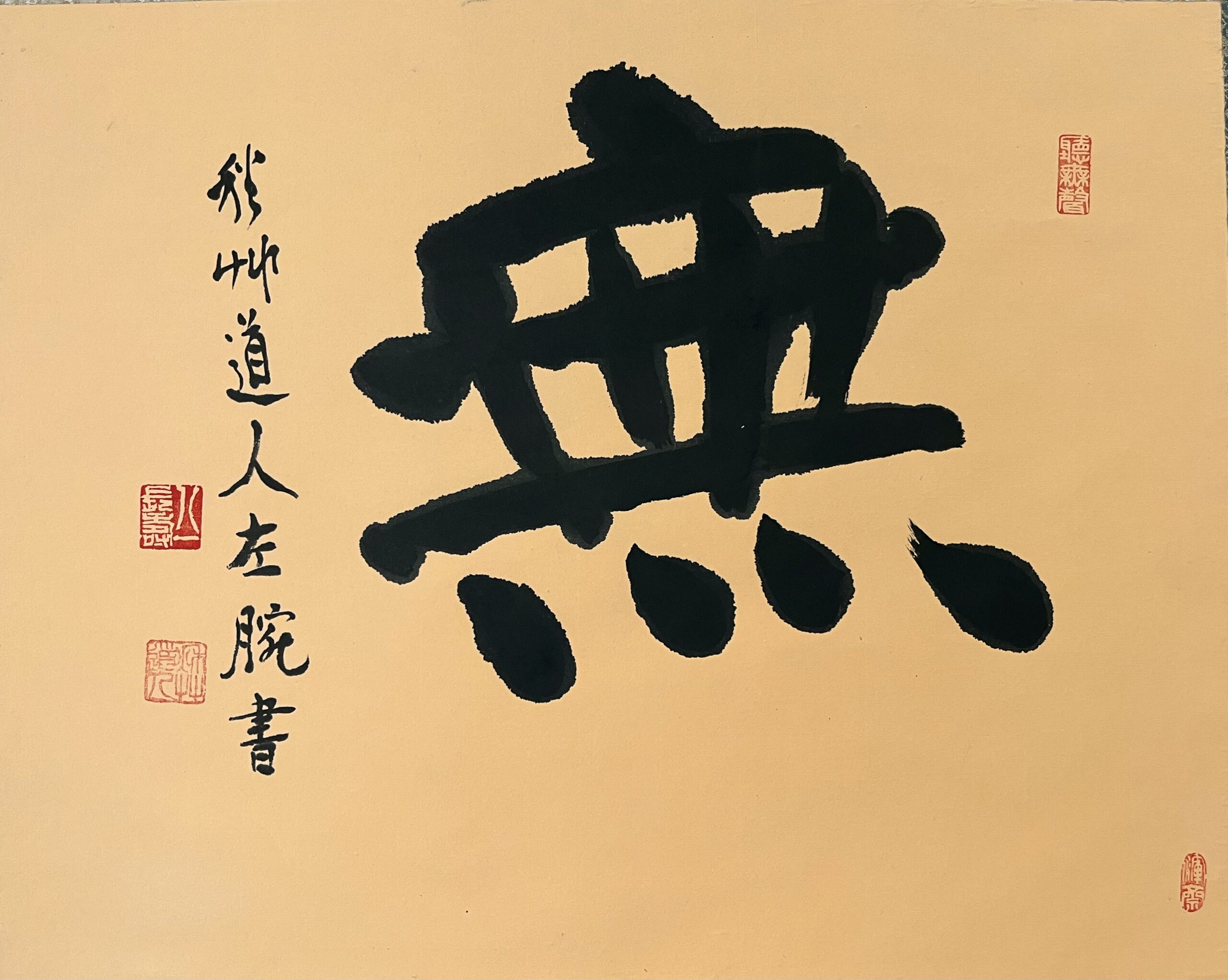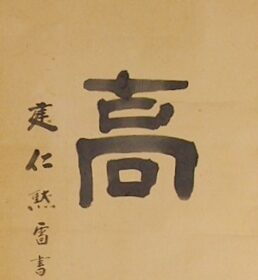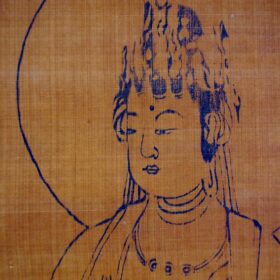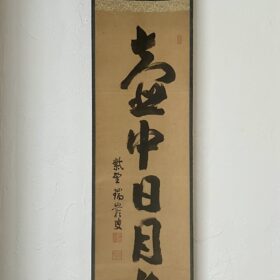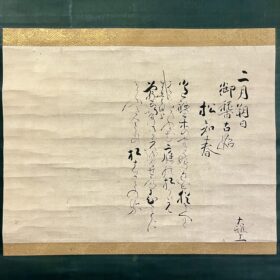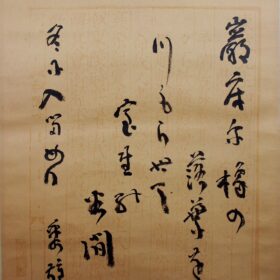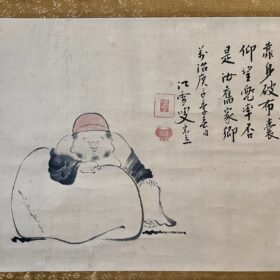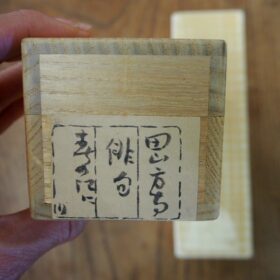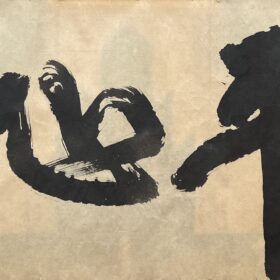本紙 縦36,4 ×横42,5㎝
軸装 縦121 ×横58,5㎝
紙本
□
会津八一
明治14年(1881)~昭和31年(1956)
歌人・書家・美術史家
新潟県新潟市出身
雅号/秋艸道人・渾斎
かの《壺中居》の看板も揮毫されています
□
「無」一文字。
八一はもともと左利きでしたが、
右手で書くことを修練、
中国、日本の書の古典を研究して、自らの独自の書世界を作り上げました。
本作品には、
「秋艸道人左腕書」と記されています。
非常に特徴的な八一の書姿と違っていますね。
素朴な感じです。
この姿の「無」は他にも作品例があり、
この作品の出現で、左手で書かれたために
八一のスタイルを離れた素朴な書姿になったこと、
それを八一も気に入っていたことがわかります。
八一が何らかの都合(病気など)で、右手が使えなくなったとは、
どの資料にも載っていませんでした。
とすると、八一は敢えて書の修練をしなかった左手で書き、
その書姿に満足していたのでしょう。
八一の書は明朝活字が基です。
「とても厳しい修練の果て」の書姿の印象です。
明朝活字の「無」は垂直と水平の線で構成されますが、
本作品はかなり右上がり。
これは晩年の特徴です。
本作品は、作り上げた型を超えたおおらかさと自由が感じられます。
地の紙が明るい色なのも、
きっと意味があるのだと思う。
印章「八一長寿」白文方印、
「秋艸道人」朱文方印は、
山田正平(1901~1962)によって刻された印章。
山田正平は、呉昌碩を尊び影響を受け、交友もした人。
この二つの印影は、それぞれ違う砡に刻まれた作品です。
本作品はもともと、大きな色紙に揮毫された作品を軸装としたものと思われます。
軸装は下手で裂も良くありません。
本紙の周囲に皺がございます。
幸いなことに、作品を損ねていませんので、
鑑賞に問題はございません。
三流の表具師が、頑張って軸装した感じです。
八一への気揮毫依頼はとても多く、大正9年(1920)に、
「書を索めらるゝは毎度迷惑の至りなり」と印刷して、揮毫依頼を断ろうとしていたらしいんです。
昭和16年の「秋艸道人會津先生還暦潤規」による色紙揮毫の値段は、金三拾圓。
当時の小学校教諭初任給の約半分です。
誂え無地箱
¥120000
消費税・送料込
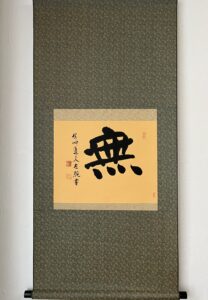
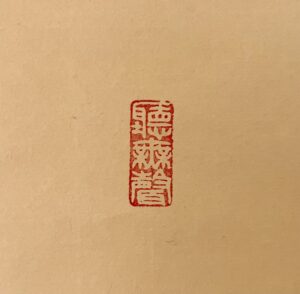
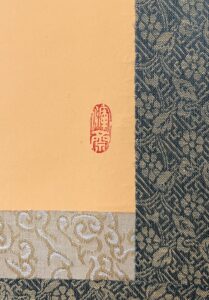
関防印
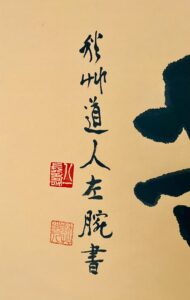 「八一長寿」白文方印
「八一長寿」白文方印
「秋艸道人」朱文方印



□