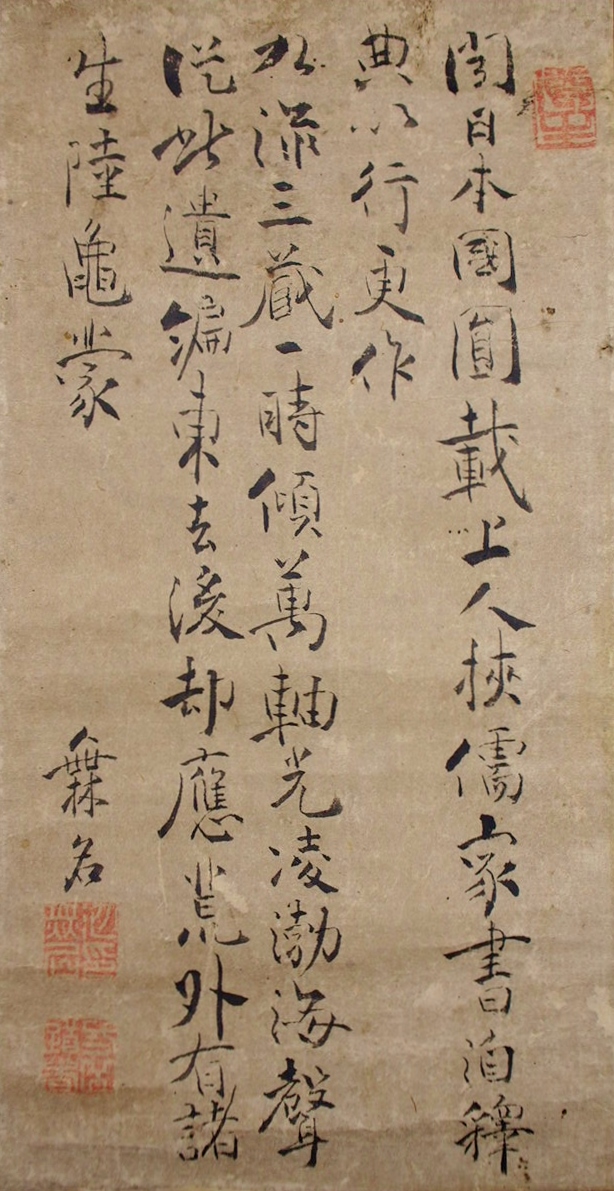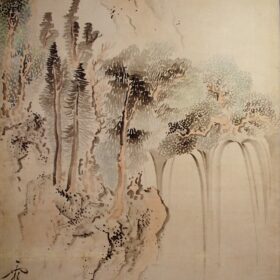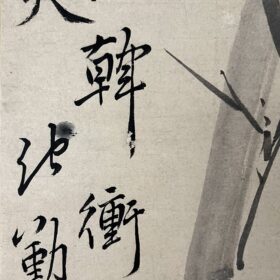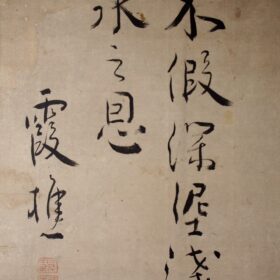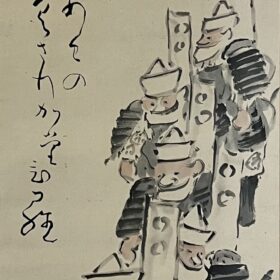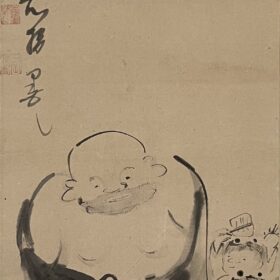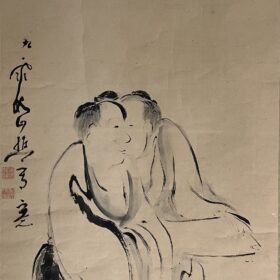本紙 31 ×16㎝
軸装 141 ×25,4㎝
紙本
□
聞日本國圓載上人挟儒家書洎釋典以行更作
九流三蔵一時傾
萬軸光凌渤海聲
従此遺編東去後
却應荒外有諸生
陸龜蒙
◆
日本国圓載上人が、儒家書と釋典を挟んで(持って)行く(帰る)のを聞き、
作ります。
非常に厳しい修行に一心に心身を傾けた。
膨大な典籍の光明は渤海の声を凌ぐのです。
儒仏の典籍が東に伝えられ、
大海の向う(の日本)に必ずたくさんの弟子を生むことでしょう。
陸龜蒙
◆
前置きの言葉の順番が入れ替わったり、
一部文字を変えていますが、
清朝の名君・康熙帝(在位1661~1722)勅撰漢詩集・全唐詩に入っている
唐の詩人・陸龜蒙の詩の一部分と、ほぼ同じ内容です。
もともとの名前〈池野〉をアレンジして、
中国様式の《池大雅》にしていたほど中国の文化に憧れた大雅にとって、
平安時代に唐に渡った僧・圓載の日本帰国に際して、
唐詩人・陸龜蒙が送った七言絶句は、
憧憬の詩であったに違いありません。
その陸龜蒙の詩に、
大雅は大雅しか表せない姿を与えています。
それは、大雅が得意とした自由奔放な書きぶりではなく、
般若心経に近い感じです。
全く力みのない、
主体性を失わない文字姿です。
派手さはありませんが、
非常に良い作品です。
橆名
《遵生》朱文長方印
《池橆名印》白文方印
《弎岳道者》白文方印
本紙に傷みがございますが、
鑑賞には全く問題ありません。
文人の書に相応しい良い表具です。
合わせ箱を入手中です。
¥165,000
消費税・送料込
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は、
大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら
一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、
その作品を愛藏されていました。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。
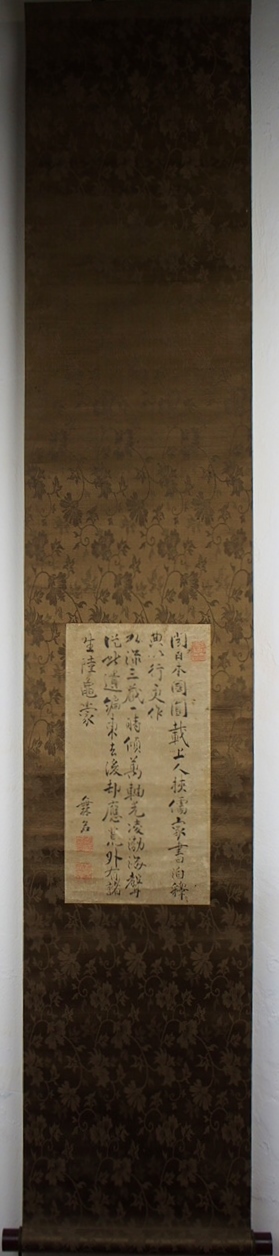
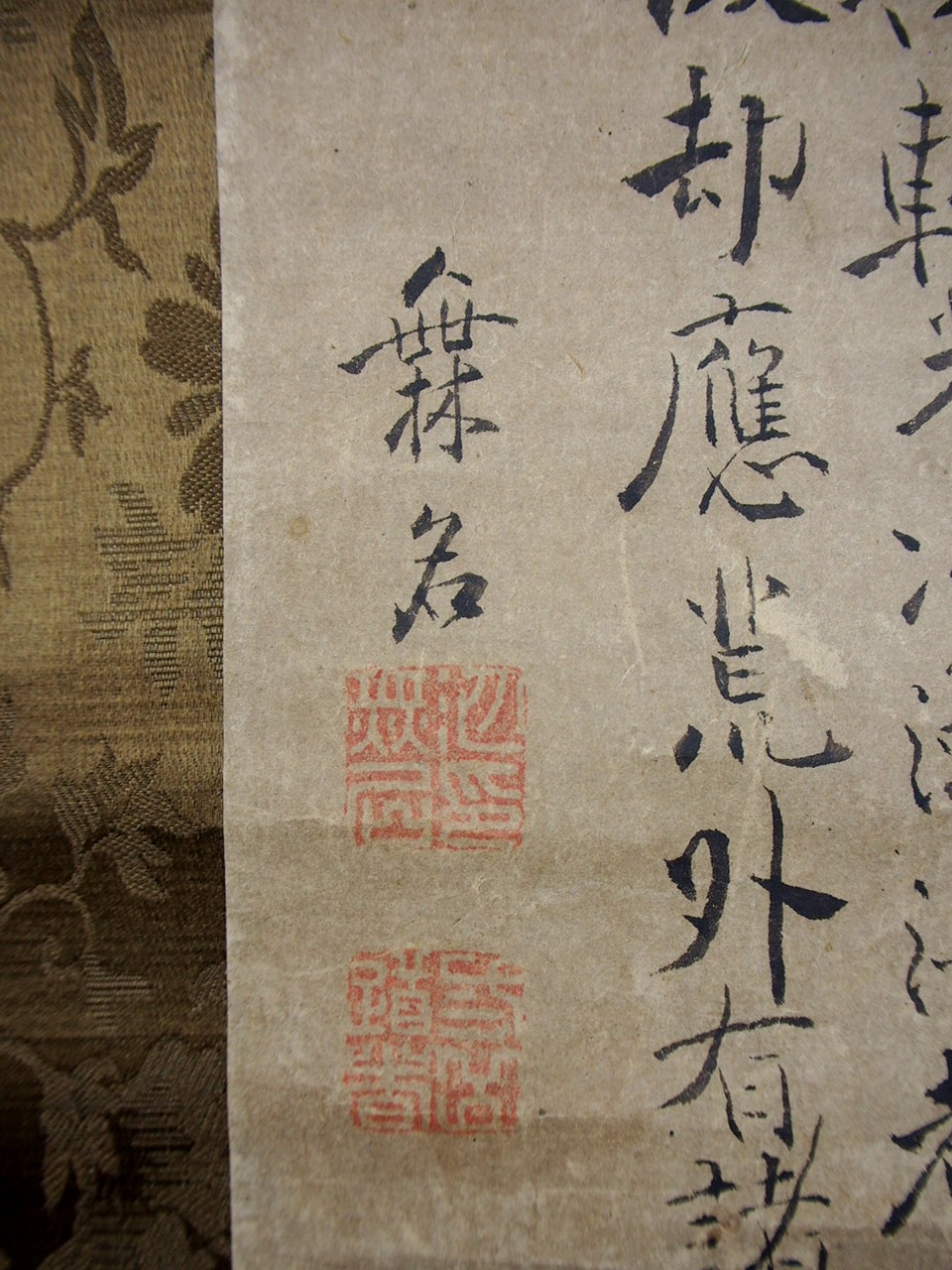
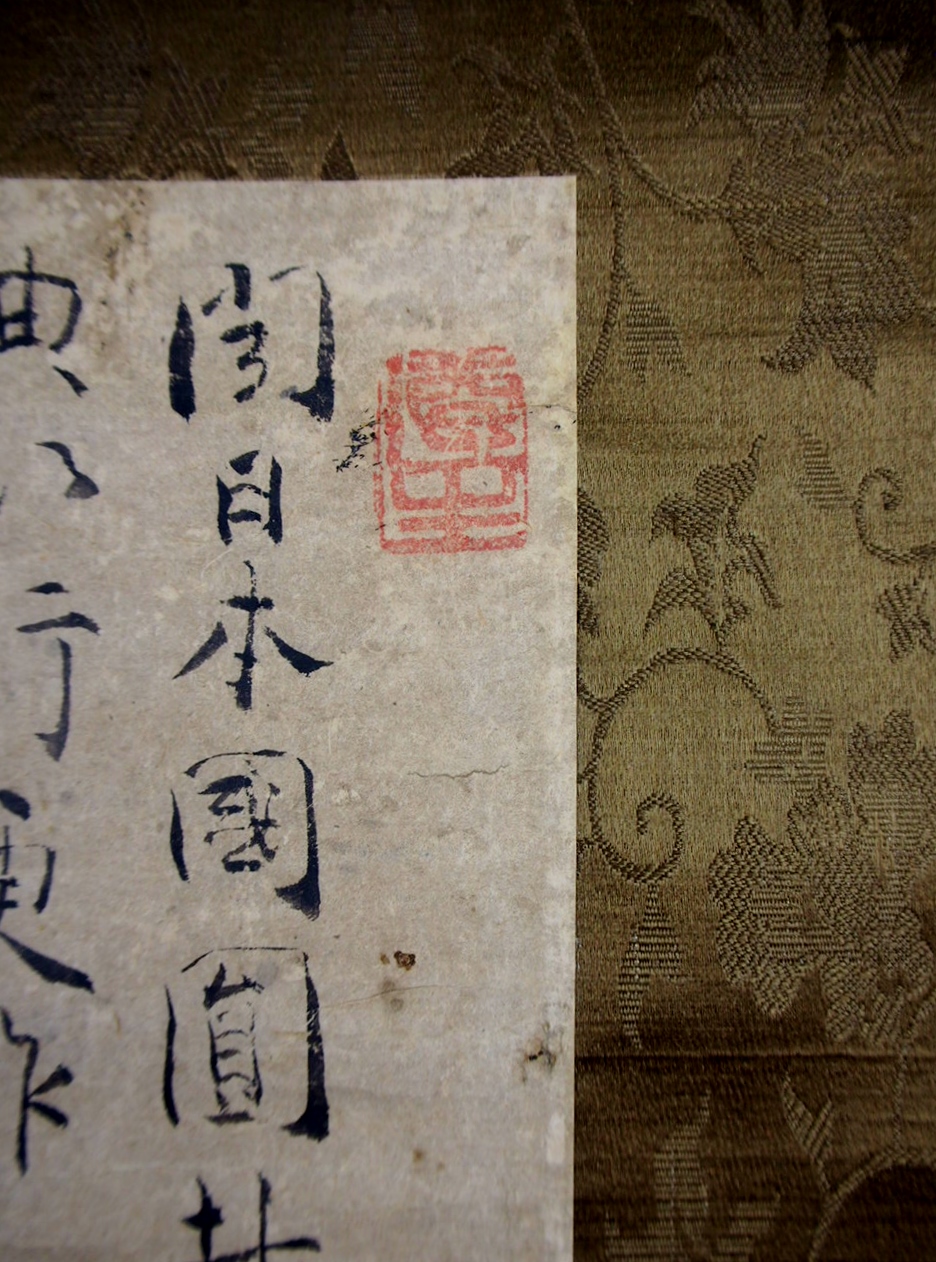

m