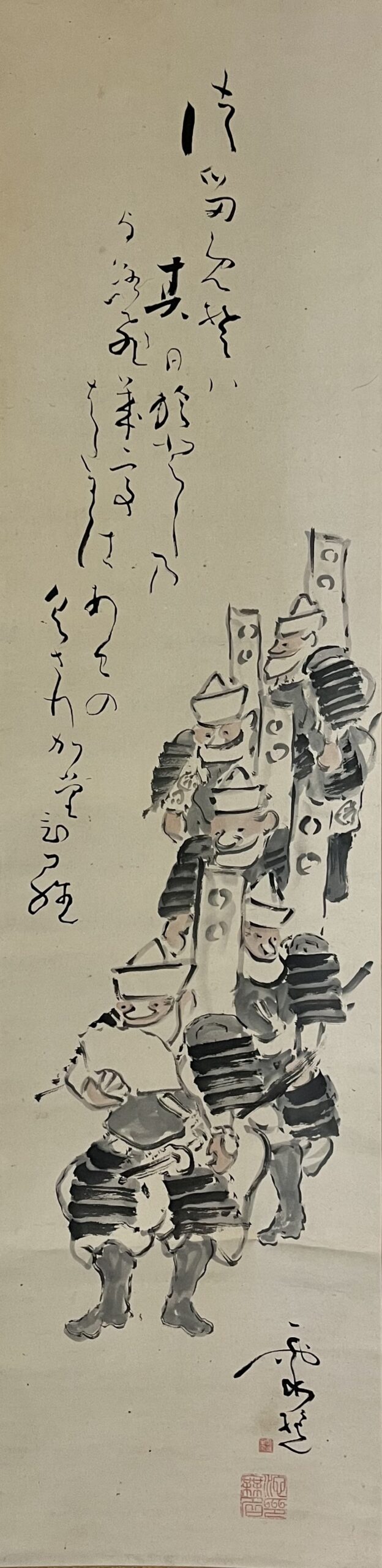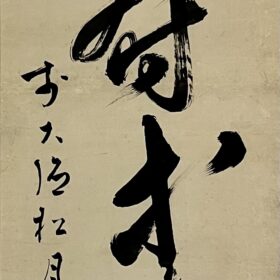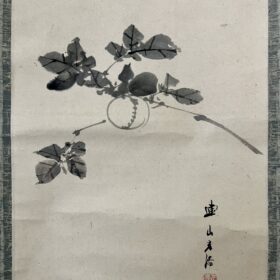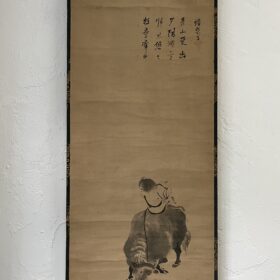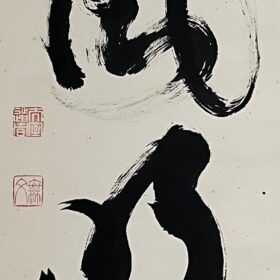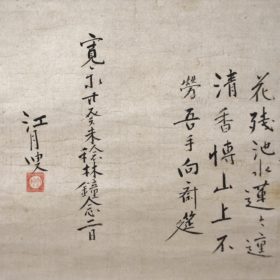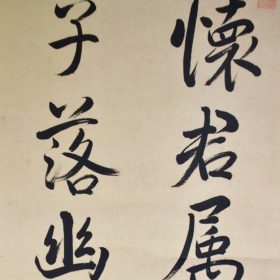本紙 84 ×28,3㎝
軸装 179 ×40,5㎝
紙本淡彩
□
つるめそは(弦召は)
其日おとしの(その日威しの)
よろひきて(鎧着て)
はたにはあせの(肌には汗の)
くさりかたひら(鎖帷子)
□
弦召(つるめそ)は、
祇園祭の神幸祭
(7/17に三基の御神輿が八坂神社から四条の御旅所まで巡行)
の時の、
建仁寺の南西付近・弓矢町からの供奉で、
警護と露払いとして、
中御座神輿の先導であったそうです。
鎧を着けた武者姿の、
江戸時代の祇園祭の代表的な風物詩でした。
夏の一番暑い盛りに、
重く風通しの無い鎧を着けて、歩いて行列しなければならない、
もの凄くキツい役割であったこと、
汗で傷んだ鎧の修復にお金がかかることなどから、
昭和四十九年を最後に、
行列から姿を消した幻の役柄です。
これは大雅が描いた祇園祭。
大雅が京都の年中行事を描いた作品は少なく、
貴重な作品です。
甲冑が暑くて、先頭の人物は扇で仰いでいますね。
「その日威し」は、
祇園祭に参加する人々が、祭りのため俄に(鎧を)誂えたことを表現したと推察されます。
「霞樵」
《大雅主人》白文小方印
《池橆名印》朱文方印
《大雅主人》は使用例の少ない印章です。
出光美術館蔵「売茶翁煎茶図」宝暦4年・32歳に捺されていて、
昭和35年発行「池大雅作品集」(中央公論美術出版)に、
もう一作品、30歳代後半と考えられる「江岸羈旅図」に確認されています。
《池橆名印》朱文方印は、
宝暦9年・37歳「梅花草堂図」(吉川英治氏旧蔵)に捺されたのが、
製作年代のはっきりした一番若い作品。
50歳代と思われる作品にも使用され、
40歳代でとても多く使われた印章です。
国宝「楼閣山水図屏風」にも使用されています。
本紙にヨゴレ、折れがございます。
無地時代箱
お問合せください



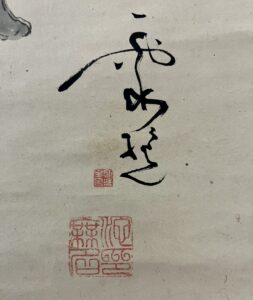


箱とタトウ。