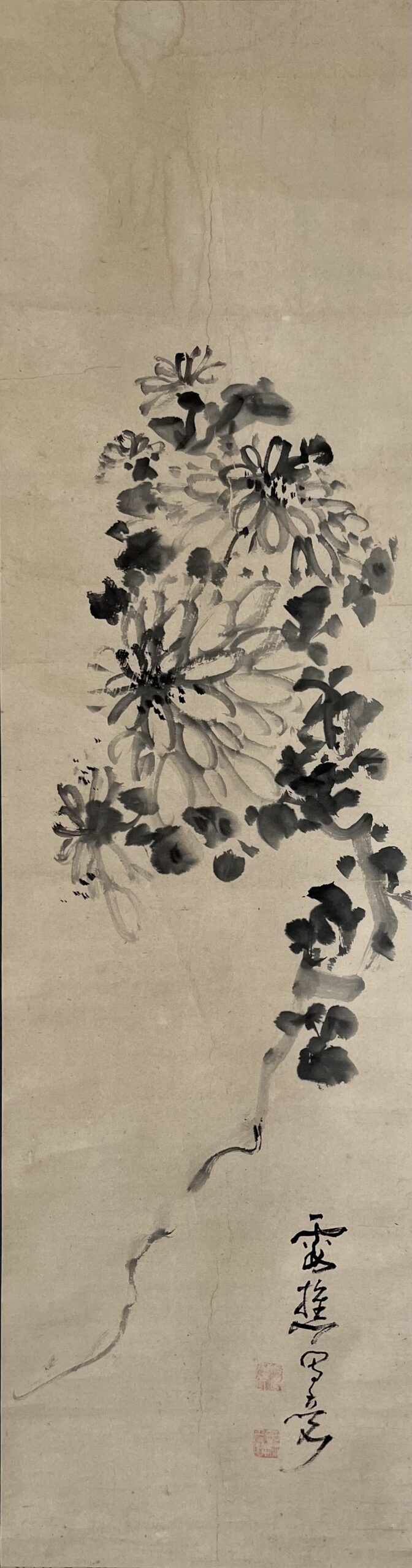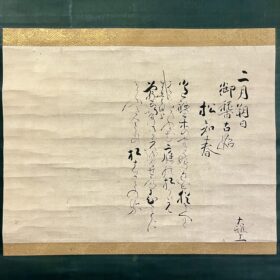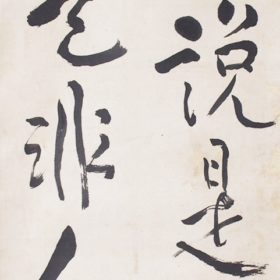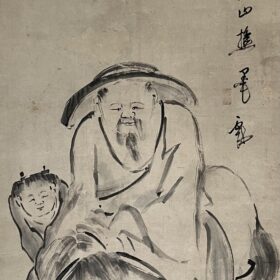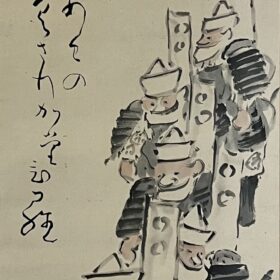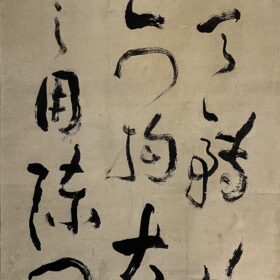本紙 104,5 ×28㎝
軸装 175 ×38,3㎝
紙本墨画
□
菊は、大雅が好んで描いた花の一つです。
20歳代の大雅は指墨(指頭/ 指や爪を筆代わりに使って描く手法)でも、菊を描きました。
晩年まで描きました。
本作品は、たっぷりと水を含んだ湿潤な筆で、
たくさんの花弁をふさふささせた中心の大輪と、
あちこちに向きを変えた脇役の花たちを描いています。
生き生きと茂る墨の葉が、
花弁の華やかな白を上手く際立たせています。
この、
茎がひょろ~としているのも、
うねっとしているのも、
大雅の菊の特徴の一つです。
「霞樵写意」
《深濘池氏》白文方印
《橆名》白文方印
この二つの印章は、
同じ印材の両サイドに彫られていて、
大抵ペアで捺されます。
年記のある作品では、
宝暦9年(1759)、大雅37歳の作品に捺されており、
30歳代と40歳代前期と考えらる作品に捺される印章です。
昭和35年、中央公論美術出版発行
《池大雅作品集》収録作品の中に、
本作品と同じ《深濘池氏》《橆名》白文方印を捺した菊図が掲載されており、
(作品№119)
花弁の描き方、花芯の点々が強い事、
一筆でシンプルに表現された葉の表現など、
本作品とよく似ています。
手数の多い筆致と、
款の《霞樵》の姿、印章から、
30歳代の作品と思われます。
紙の下の板目が墨に現れた部分がございます。
依頼に応じて即興で描かれた作品なのかもしれません。
キツい傷みを修復して仕立て直した後に、
更に、
本紙が濡れた輪染み跡がございますために、
格安です。
画像でご確認ください。
力強い筆致で、生命力に溢れます。
仕立て直した時に誂えたであろう、
非常に手のかかった差し箱。
昭和5年の極めが、蓋裏に書かれています。
¥80,000《お問い合わせいただき中》
消費税・送料込
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は
大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら
一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、
その作品を愛藏されていました。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

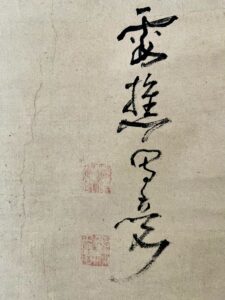
落款脇傷み痕

紙の下の板目が現れています。
依頼に応じて即興で描かれたのかもしれません。
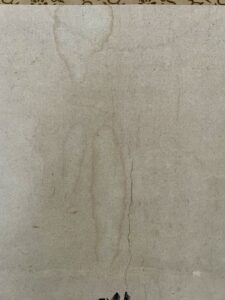
シミ
 傷みや汚れ
傷みや汚れ
 軸先
軸先


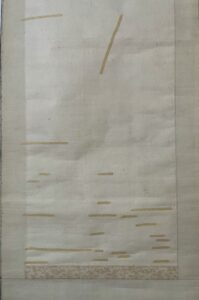
軸装裏面、修復痕と汚れ




引き蓋の手がかりは、黒柿のポッチです。