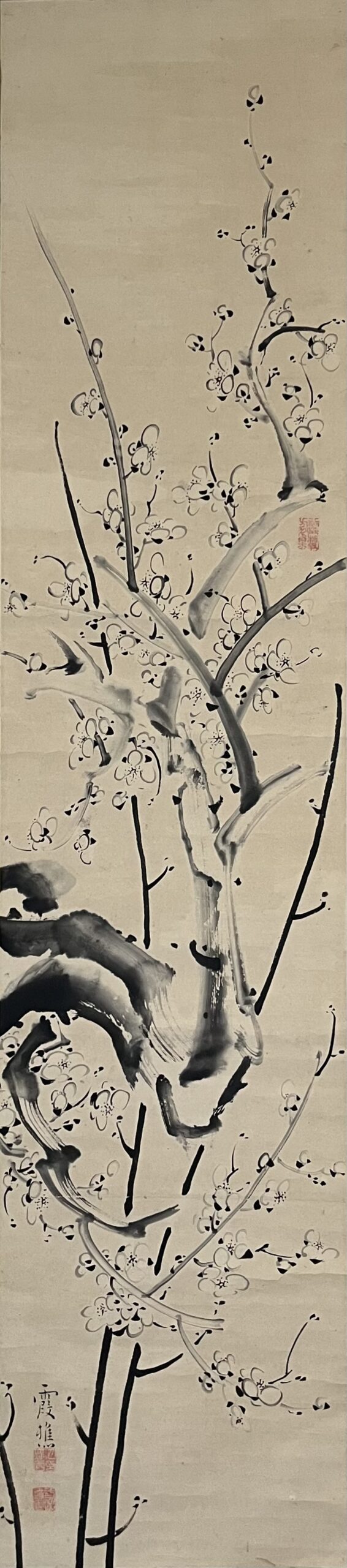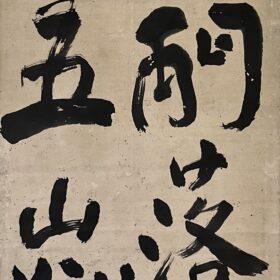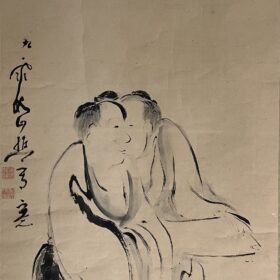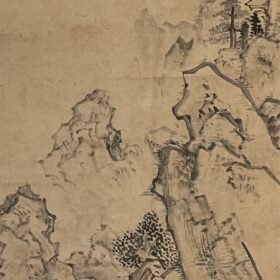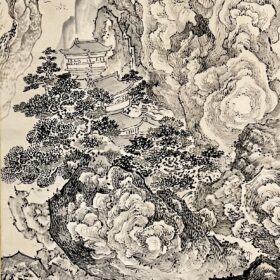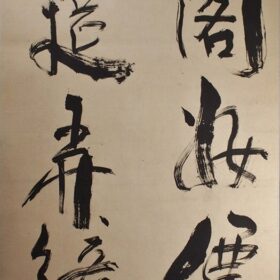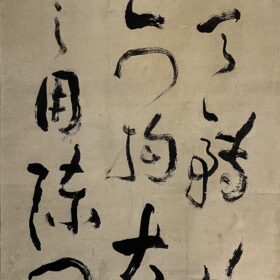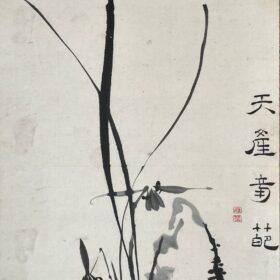本紙 約132,5 ×29,4㎝
軸装 約202 ×47,4㎝
紙本
□
長い紙面の中ほどに、とても太い幹が左から横に姿を見せて、
鋭角に曲がって垂直に天を目指します。
水を、これ以上なくたっぷり含んだ太い墨の筆致の横線。
そのまま筆に水だけ含ませて、
潤いに満ちた枝が伸び伸びと天に向かいます。
一方で、もう一枝は下に向かいます。
枝は波のように、4つの孤を連ねて描かれます。
上の枝にも、下の枝にも満開の白梅。
今を盛りの花の生命。
見惚れる美しさです。
青墨で早い筆致で描かれ、
これ以上時間が経つと散り始めるであろうことを感じさせます。
太い幹の黒と上下の花の白のコントラスト。
下から若い枝が二本空間に侵入し、
ぞくぞくする緊張感です。
自然は、ただあるだけで美しいです。
写真のない250年以上前は、その姿を映し、その場にいない人に伝えることも、
絵を描くことの一つの命題であったでしょう。
それだけではなく、
自然の姿に揺さぶられた絵師の感動を、どうしたら紙に落とし込めるのか。
どうやったら自分の感動が、
見てくれる人の心を動かせる作品になるのか。
大雅はそれだけを追求していたように思います。
年を重ねた老木の深い味わいを、限界まで省略した二本の太い墨、
潤いに満ち屈曲して天を目指す枝の姿、
こぼれんばかりの満開の白梅、咲く喜び。
黒々と伸びやかな若い枝の空間バランス。
梅の花が好きだった大雅の作品の中でも、特に優品と存じます。
よくよく見ると、絵が描かれていない空白部分に、
極く薄い空気のようなものが掃かれています。
薄い藍を刷く作品はありますが、初めて見た技法です。
とても明るい月夜かしら。
款記「霞樵」
関防印「前身相馬方九皐」朱文長方印は、
30才代から使い始め、最晩年まで使い続けます。
池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)に収められた811作品中、
155作品に捺されています。
現在国宝や重要文化財にしていされている作品にも、
数多く使用されています。
最も使用頻度の高い印章です。
「池橆名印」白文方印
「弎岳道者」白文方印
この2印は、30才代後半から使われ始め、40才代で非常に多く使われ、
50才代、最晩年まで使われた印章です。
ペアで捺されることが多いです。
池大雅作品集(昭和35年・中央公論美術出版)掲載682画作品の内、
64作品にこの2印がペアで捺されています。
同じ墨梅図、同じ印章の使用された作品が、作品集に収録されています(№461)。
そちらは、款記に制作年がしるされていて、
明和5年(1768)、大雅46才の作品。
細い筆で丁寧に優しく書かれた書体も、本作品と似ています。
本作品も円熟期40才代後半の作品でしょう。
本紙に折れは、小さな虫跡、などがございますが、
鑑賞に全く差し障りのない良いコンディションでございます。
無地箱
¥385000
消費税・送料込

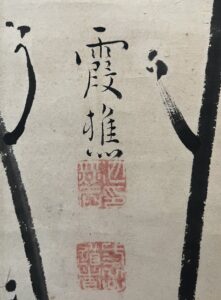
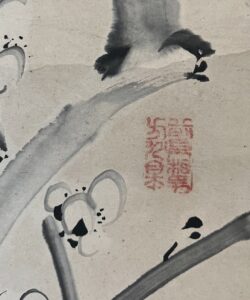
款記「霞樵」・「池橆名印」白文方印「弎岳道者」白文方印/ 関防印「前身相馬方九皐」朱文長方印
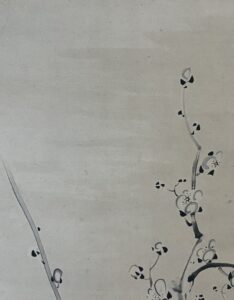 霞のような薄い空気が表現されています。
霞のような薄い空気が表現されています。
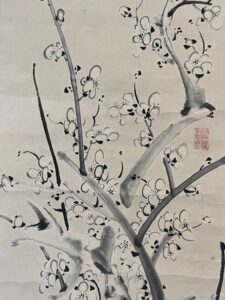

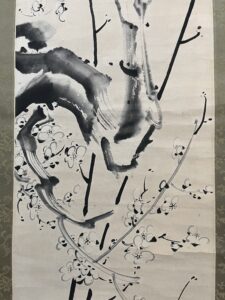 紙に継ぎ目がございます
紙に継ぎ目がございます
 虫穴修復痕
虫穴修復痕



□
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら
一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、
その作品を愛藏されていました。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。