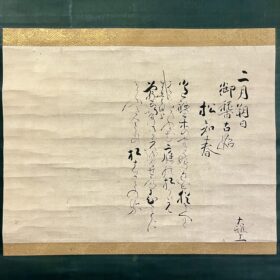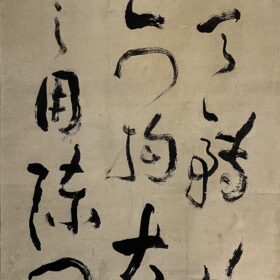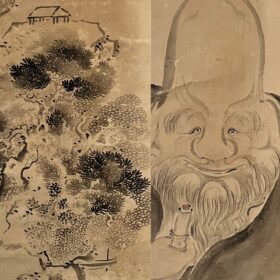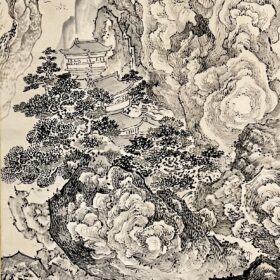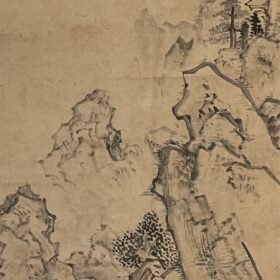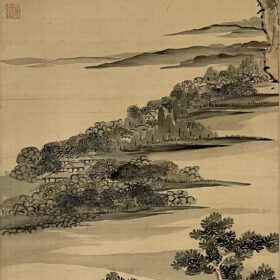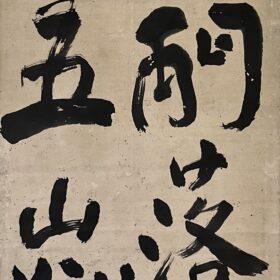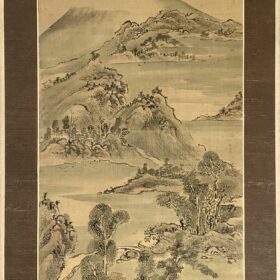本紙 約122,5 × 36,2㎝
軸装 約205 × 39,3㎝
紙本墨画
□
釈迦如来と、普賢・文殊菩薩を描いた三福対。
こんな三尊像見たことがない!
お釈迦様は、
厚い唇、重い瞼、大きな鼻、無精鬚。
寝起きの近所のおじさんみたいです。
衣は極端に省略され、
筆の勢いが激しく、描線が擦れています。
普賢菩薩は後ろを、
白象は真横を向いています。
知恵を象徴する巻き物を捧げ持った文殊菩薩は、
口を開けて屈託なく笑っています。
ぬいぐるみみたいな顔の、可愛い笑顔の獅子。
普賢菩薩のお供の象は、
同じ世代、同じ京都で活躍した伊藤若冲の描く象にも似て、デフォルメされきっています。
凄い!
これ以上は削れないところまで削ぎ落した、筆数の少ない筆致。
三幅とも、
あまり太くない筆で、薄墨でムラムラに余白を埋め、
塗り残しで光輪を現しています。
水分をたっぷり含んだ潤った、最小限の筆で描かれます。
大雅にしかできない三尊像表現。
神々しくはないけれど、見る者を絶対に見捨てない、
どんな人の心をも抱えて寄り添ってくれます。
三幅並べると、
お釈迦様の肩の太い輪郭線と、一息で描かれた強い衣文が聳える山のようで、
お釈迦様が、異次元の高さにいらっしゃるように、
見える構成です。
慈雲尊者(1718~1804)の賛を持つ、
本作品と非常によく似た文殊菩薩像が、
「池大雅作品集」(中央公論美術出版/昭和35年/№502)に掲載されています。
個人蔵で、ここに作品をご紹介できないのが残念ですが、
ほとんど瓜二つ!です。
作品集には、811作品が収められていますが、
この文殊様以外、
お釈迦様も、普賢菩薩も、三尊像作品もありません。
本作品は
非常に珍しい大雅の三尊像です。
落款はありません。
大雅の書いた般若心経作品は、名前を記さない(款記のない)作品が多いです。
仏への崇尊により、自署を控えたものと推測しています。
三幅対の大作でありながら、本作品に款記がないのもそのためでしょう。
大雅は非常に信心深い人でした。
釈迦尊像には「霞樵」朱文聯印、
「玉皇香案吏」朱文方印が、下部中央に捺され、
両菩薩像には、「霞樵」朱文連印と「池橆名印」白文方印が、
それぞれの下部左右端に捺されています。
「霞樵」朱文連印は30歳代から最晩年迄使われ、
作品集掲載作品811点中、145点と、
最も使用頻度の高い印章の一つ。
「玉皇香案吏」朱文方印は、20才代から40才代まで使い続けた印章です。
上記作品集中、71作品に捺されています。
詳しくは
大雅の印③ 「玉皇香案吏」前編
に、記してございます。
ご参照ください。
もう一つの「池橆名印」白文方印は、
かなり似た印影の印章が複数ございます。
少なくとも、2つ確認されています。
いずれも、30才代後半から最晩年まで使用されています。
本紙に傷んだ箇所を非常に丁寧に修復した形跡がございます。
特に釈迦尊像は、修復痕が多いです。
画像でご確認ください。
折れもございますが、
作品の価値を損なうものではありません。
非常に上等な裂を使った贅沢な軸装と、
内箱に古裂のタトウまで備えた誂え箱が、
旧蔵者の、作品に対する情熱と尊敬を表しています。
細谷立斎(1831~1911/貫名海屋門下の南画家・古書画鑑定家)の
明治28年の鑑定付、二重箱。
《お問い合わせください》



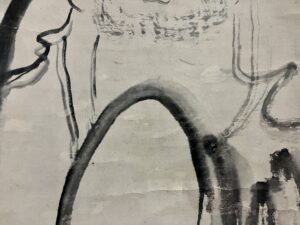
釈迦尊像傷み修復仔細




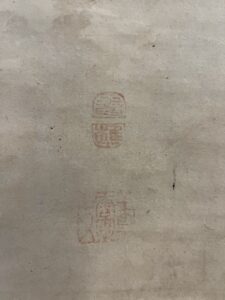
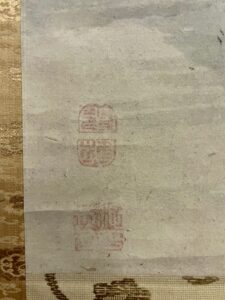
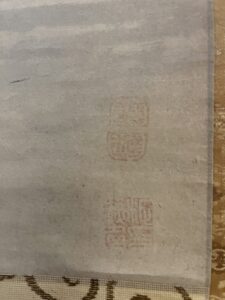
□
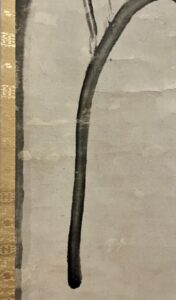
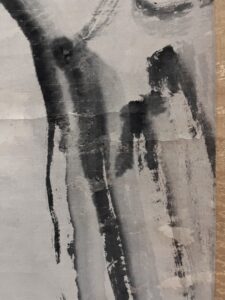

釈迦尊像傷み画像

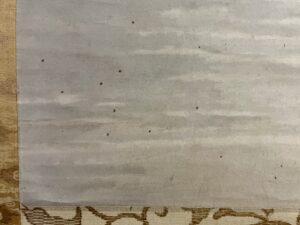
文殊菩薩傷み汚れ

軸先・技巧細工象牙


内箱・内箱蓋裏極書


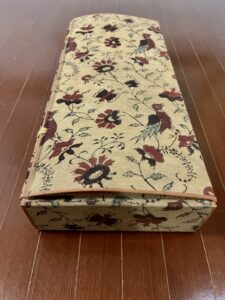
内箱古更紗タトウ




外箱
□
池大雅
享保8年(1723)~安永5年(1776)
諱/橆名(ありな)・勤
字/貨成・公敏
号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他
京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。
当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。
20才代ですでに名声が高く、
旅が好きで日本各地を旅したため、
日本各地に大量に贋物が存在しています。
近世の絵師で、
国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、
現在ではあまり知られていません。
文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。
川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら
一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、
その作品を愛藏されていました。
国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。